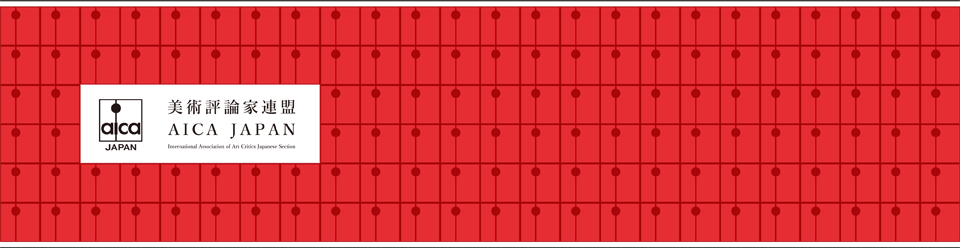批評とジェンダー
笠原美智子
聞き手:土屋誠一 きりとりめでる
土屋:近年、「表現の現場調査団」の活動や、セクシュアル・ハラスメントの告発と被害者の擁護、ジェンダー平等への明確な取り組みなど、ジェンダー不公正を是正するような活動が、ようやく本格化してきたように思います。私自身も、女性作家の表現の自由の擁護に、意識的にコミットしたこともあります。このような現状は、被害者が存在する以上、諸手を挙げて喜ぶべきことではありませんが、声なき声として押し込められていたかつてと比して、被害者が実在することが可視化され、加害者が相応の社会的制裁を受けるという点では、たった10年前程度の近過去と比べても、大きな前進だと思います。笠原さんは、美術におけるフェミニズム/ジェンダーの問題を、展覧会「ラヴズ・ボディ」(1998、2010年の2回とも!)をはじめとしたキュレーションや文筆活動によって切り拓いていったオリジネーターのお一人ですが、笠原さんがこうした問題に取り組み始めた当時は、社会運動の側面もさることながら、「思想」の問題も、そこに多く含まれていたように思います。
今日のアクションは、SNSの一般化によって、「思想」の共有よりも「実践」の共有のスピードが非常に早いことが、いままでのフェミニズム/ジェンダーの動向と一線を画すように思います。フェミニズム/ジェンダー問題における「思想」と「実践」とは、両輪が同期するのがベストだと思うものの、問題も待ったなしで瞬間的に共有される現状、この両者を実際に両立させるのは、現実的には困難が少なくないように思います。
きりとり:そうですね、今日の「思想」にかんして、重版された『文藝 2019年秋号』、『現代思想2020年3月臨時増刊号 総特集=フェミニズムの現在』、最近創刊された『 i+med(i/e)a』や展覧会といった遅いメディアを通して、今までのフェミニズムを振り返り、現実践が思想的にどう考えうるか試行錯誤されていると思います。
土屋:そのような観点を踏まえて、近年のフェミニズム/ジェンダーに関わるアクションについて、先駆者である笠原さんのお立場から、どのように見えているのか、ぜひ伺いたいです。
笠原:近年の「フェミニズム/ジェンダーに関わるアクション」は、わたしたちがこの30年間続けてきたジェンダーの視点からの展覧会実施に接続しているというよりも、2017年に映画プロデューサーのワインスタインのセクハラを告発する「#MeToo」運動が、アメリカはもとより世界的なセクハラ告発運動として展開していったことに端を発しています。日本でも同年、ジャーナリストの伊藤詩織氏が日本では初めて顔と名前を出して強姦被害を告発しました。翌年2018年には財務省の福田淳一事務次官が女性記者へのセクハラで辞任に追い込まれています。写真家・荒木経惟氏が長年のモデルであったKaoRiさんからパワハラとセクハラを告発されたのも同年です。
長らく被害者に我慢を強いてきた日本でやっと、被害者が沈黙を破り声をあげ始めました。その勇気が賞賛される一方で、声をあげた女性に対して心無い非難や誹謗中傷が浴びせられ、反感を買うこともいまだ多々あります。世界経済フォーラムが毎年発表している、各国の男女格差を測るジェンダーギャップ指数の2021年の日本の順位は、156カ国中120位、先進国ではダントツの最下位、アジアでも韓国や中国、ASEAN諸国よりも低い結果でした。わたしたちはそうした差別社会に生きていることを自覚することは重要だと思います。だからこそ近年のこうした活動がやっと立ち上がり、表現に関わる現場の現状を詳らかにし、今まで被害を受けた人たちの沈黙の上に有耶無耶にされてきた行為が、それは許されないハラスメントであると加害者に自覚を垂らしめる、非常に貴重な活動だと思います。そんなことをつらつら書いていたら、林道郎さんのニュースが飛び込んできました。言葉を失いました。残念です。学生と性的な関係をもった時点でアウト、弁解の余地はありませんが、このケースがいかにも現代的なのは、「時間を経たことでセクシャルハラスメントを周囲に話すことができるようになり、『あれは性被害だった』と自覚するようになった」(註1)と告発者が取材に答えていることです。わたしは1996年の「ジェンダー 記憶の淵から」展で取り上げたキャリー・メイ・ウィームスの〈今なら何をされていたかわかる そして私は泣いた〉という作品を思い出しました。彼女はアフリカ系アメリカ人がどのように「白人」によって扱われ表象されていたか、過去の写真と言葉を重ねることで差別の在りようを鮮やかに描き出しました。時間を経て大人になることで過去の行為の意味を知ることは誰しも経験することだと思います。その意味を理解し名前を与え告発する、それを周囲が受容れ応援する、そうした素地が日本社会にすでに息づいていることを明らかにしてくれました。ただし、事実の検証や議論の深まりなどまったくないままに、SNS上で同じ文章が繰り返されて一方的な方向へと凄まじい速さでネット世論が形成される、その暴力に怖気を振いました。TwitterもfacebookもInstagramもやりませんが、わたしは君子ではないけれど、危うきに近寄らずの戒めをますます強くしました。
きりとり:近年、女性のアーティストを取り上げた展覧会が注目を集めていますが、笠原さんはどのようにご覧になられていますか。
笠原:今年は女性アーティストの展覧会が目立っています。東京藝術大学大学美術館陳列館での「居場所はどこにある?」展、京都国立近代美術館の「ピピロッティ・リスト:あなたの眼はわたしの島―」展、森美術館の「アナザーエナジー 挑戦しつづける力―世界の女性アーティスト16人」展、国立国際美術館と東京都現代美術館「Viva Video! 久保田成子」展、ポーラ美術館「ロニ・ホーン:あなたの中に水を感じる?」展等々、ざっと思いつくままでもこれだけの展覧会が挙げられるのは近年あまりないことでしょう。もちろん、多くの展覧会が開催されている中でこの他の展覧会は主に男性作家なのですから「女性の展覧会が多い」と騒ぎ立てするうちはまだまだであることは言うまでもありませんが。
このような活況にわたしのこの約30年間の仕事は接続しているのでしょうか。そもそもわたしは何をしてきたのか(註2)。改めて表にしてみると、我ながら精力的に展覧会を企画・実施してきたかがわかります。世界的にみても、わたしほどやりたい展覧会を企画し実施できた幸運なキュレターはいないと思います。加えて頼まれ原稿や委員・審査員などの仕事があり、殺人的なスケジュールだったことは確かです。いま、帯状疱疹後神経痛と耳鳴り・肩こり・腰痛に苦しめられているのは、この時期蓄積した疲れのせいだと断定しています。
わたしの仕事の軸は「アメリカ近代写真」、「ジェンダー」、「現代写真・美術」に大別できます(参考資料1)。ジェンダーの視点から企画した展覧会とその意図をおさらいすると、まず、1991年の「わたしという未知へ向かって 現代女性セルフ・ポートレイト」展が挙げられます。男性が描いてきた女性像、娘・妻・母としての女役割や受け身の待つ女、ファム・ファタール、被害者としての女性像といった女性のステレオタイプの表象を分析しその問題点を明らかにし新たな女性像を模索する展覧会でした。今から見るとジェンダーの視点からの展覧会としては女性対男性という二項対立に留まる試みでしたが、わたしは1980年代の4年間をアメリカで過ごしていたので日本の状況を把握してなかったのですが、日本の美術館としては初めてのジェンダーの視点からの展覧会と評価されることになりました(註3)。
1996年の「ジェンダー 記憶の淵から」展では女性の表象の問題に加えて、私たちが生きていく上であらゆる事柄にジェンダーの問題は関わってくることから、身体や加齢、セクシュアリティ、民族や宗教や政治や戦争といったテーマの作品を取り上げています。前回が欧米の白人作家中心だった反省から、アジアや中東、アフリカ系の作家も意識的に含めました(註4)。
「ジェンダー 記憶の淵から」展で取り上げたテーマの内で特に身体に焦点を当て、1998年に「ラヴズ・ボディ ヌード写真の近現代」展を開催しました。従来の男性の性的幻想を表現したヌード写真を脱構築して新たな身体表象を探るという展覧会でしたが、わたしが企画した展覧会で最も賛否両論が噴出し話題になった展覧会でした。通常、評価しない作品や展覧会は取り上げない・書かないことで自らの態度を示し展覧会評は否定的な言及をほとんどしないのが日本では一般的ですが、この展覧会はそのような日本の美しい姿勢を崩してでも言わざるを得ないほど生理的に嫌だったのでしょう。感情的な反発にあいました。「行き過ぎたフェミニズム」に対しての「バック・ラッシュ」が起こっていたのですが、この展覧会も含めた「ジェンダー論争」については「イメージ&ジェンダー研究会」のホームページで詳細を見ることができます(註5)。
「ラヴズ・ボディ ヌード写真の近現代」展で取り上げたテーマの中でも、特にセクシュアリティについてより深く考察するなかで、エイズをめぐる状況と作品は特に重要だと思われました。2010年に「ラヴズ・ボディ 性と生を巡る表現」展として実現しましたが、開催までに12年もかかってしまったのはやはり、今までの展覧会がわたしが一個人として現代を生きる女性として当事者であったのに対して、エイズを巡る作品においては、同時代を生きているという以外、当事者性を持たなかったことが原因だと思います。エイズを巡る表象を契機に作家がどのような立場で、誰に対して作品を発表するのかまで問われるようになりました。この点は強調してもしたりないことはないと思います。この展覧会の入場者数は23192人にとどまりましたが、差別的な言動で物議を醸した石原慎太郎都知事の下での開催であり、冒頭、都の行政マンへの不満を書いてしまいましたが、このような展覧会は特に行政側の理解がないとできなかったことは申し添えておきたいと思います。
ジェンダー展を準備するうちに、わたしの関心は欧米の作品から徐々に日本やアジアへと比重が移っていきました。欧米の美術・写真については知っていても足下のアジアについては何も知らないではないか、と遅まきながらの自覚でした。ただ日本の現代写真・美術については90年代から折に触れて展覧会を組織し続けてきましたが、アジアの場合は作品だけでなく、その作家を培った社会的背景までも学ばなければならず時間がかかりました。2017年の「ダヤニータ・シン インドの大きな家の美術館」展と、2018年3月に定年退職したのち、わたしの企画を引き継いでくれた若い学芸員・山田裕理氏と共同キュレーションの2018年10月からの「愛について アジアン・コンテンポラリー」展がその成果です。
幸いなことにこうした企画を支えてくれた個人や機関は多々ありますが、特に若桑みどり氏に1991年の「セルフ・ポートレイト」展図録の論考を依頼したのがきっかけで、千野香織氏、池田忍氏、香川檀氏や北原恵氏等と1995年に立ち上げた「イメージ&ジェンダー研究会」は当時隔月に1度研究会を開き、機関紙を発行するなど活発に活動し、のちに美術館でのジェンダー展の同志でもある小勝禮子氏も加わり精神的な支えでした。わたしは最近サボっていますが、この研究会は現在も続いています。
わたしたちのこうした仕事が現在の活動に多少なりとも繋がっていると願ってやみません。これからは、自分にあたえられた場所でできる限りのことをして、若い人たちの様々な試みに少しでも力になり、少なくとも邪魔をしない。それが、できる限りのことをやってきたつもりでも、ジェンダーギャップ指数がこれだけ低いままにしてしまった一人の大人の責任だと思います。
註1)「美術評論家連盟会長で上智大教授の林道郎、元教え子の女性がセクハラで提訴。10年にわたり関係」『美術手帖』オンライン、2021年9月20日、https://bijutsutecho.com/magazine/news/headline/24592
註2)誤解がないように予め断っておくと、美術館で最も時間や労力を費やされたのは、学芸員として時間をかけるべき展覧会準備や作品収集業務ではありません。東京都や財団、写真界との調整、美術館内部での人間関係の対処、後年になるとマネジメントに多くの時間が取られました。アーティゾン美術館にきてつくづく思うのは東京都や財団との調整がいかにわたしを疲弊させていたかということです。[笠原]
註3)東京都写真美術館一次開館での仮の建物での展覧会にも関わらず、1万人に迫る9807人の入場者と5大紙すべてがこぞって展覧会評を掲載するなど話題となったなりました。[笠原]
註4)前回と同じく多くのマスコミに取り上げていただき、入館者数は27529人でした。[笠原]
註5)「ラヴズ・ボディ」展の入館者は37044人で、大阪のサントリー・ミュージアム〔天保山〕にも巡回しました。[笠原]