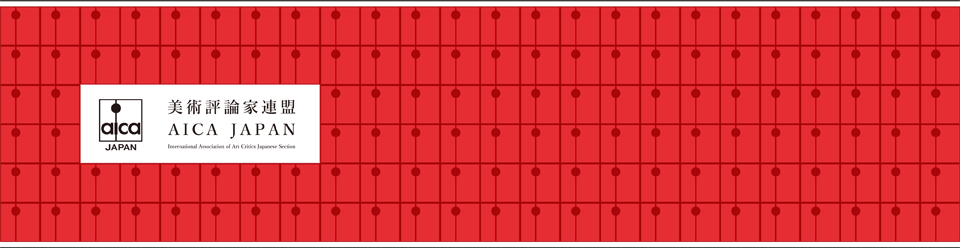2004年は美術評論家連盟結成50周年に当たり、それを記念するイベントを企画しよう、と同連盟の常任委員会で発議され、「五〇周年記念事業委員会」が組織され、委員に谷新、南條史生、水沢勉、清水敏男の4名が会員のなかから選ばれた。幹事は清水が担当することになった。その後、委員会での議論による素案が常任委員会で承認され、記念シンポジウムを開催する運びとなった。シンポジウムの名称は「日本の美術批評のあり方」となった。
また、その計画は同時に出版計画を伴うものであり、それは美術評論家連盟編『美術批評と戦後批評』という書名で2007年に出版社のブリュッケから刊行されている。その経緯については、編集委員のひとりである水沢が「編集後記」として同書の巻末に記している。
ここでは、それ以後を意識して、わたし自身の個人的な所感を簡単に記しておきたい。
2008年の「リーマンショック」と日本では呼ばれている金融危機以後、日本ばかりでなく、世界全体の経済状態の流動化が、「新自由主義」をさらに加速させ、既存のイデオロギー的な構図を一気に陳腐化させ、「美術批評」の舞台をもまったく変貌させてしまった。いまわたしには、シンポジウムでもしばしば言及されていた「メディア」のあり方が、完全に異質なものになってしまったという実感がある。少なくとも新聞雑誌といった紙媒体、あるいはテレビなどの既存の主要メディアに「美術批評」の場が存在すると確信している「批評家」「評論家」は、少なくとも前景に多数は存在せず、シンポジウム冒頭で当時連盟会長であった針生一郎が望んだ「論争」の場もなければ、仮にあったとしても、それを拡大深化させる状況はほぼ皆無に近くなった。いま前景に大きく存在するのは、ポスト・トゥルースのポピュリズムの利益誘導の論理である。シンポジウムで登壇者のひとり光田由里(当時は非会員。現在会員)が指摘した「レヴュー」ではなく「プレヴュー」の広報宣伝的な言説の、SNSなどを主要な伝達手段とする言説のウェブ空間での横行である。
また、「美術館批評」が必要であることも、針生一郎は指摘していた。シンポジウムではほぼそれそのものが論点として俎上にあげられて議論されることはなかったものの、やはり針生のいう「ミュージアム・ピープル」が制度に取り込まれずに自由に、責任をもって発言すべき批評の場が必要であるという危機感の表明であったと思われる。その背景には2001年に施行された独立行政法人国立美術館によって文化庁に所掌される「国立美術館」の変化があった。ちなみに、美術評論家連盟も独立法人国立美術館もともにその事務局を、後者のひとつである東京国立近代美術館内に設置している。見方によっては、奇妙な呉越同舟的状況だが、それを批評的な緊張という風に積極的に意識化する気配はいまのところないようだ。
21世紀の日本の美術状況のなかでのもっとも大きな変化のひとつは、さまざまな芸術祭が日本各地で催されるようになり、急速に国内外でその存在が注目されるようになったことであろう。現在、国が奨励するインバウンド政策もあって、いくつかの芸術祭は活況を呈している。かつてのオフ・ミュージアム的な動きを孕んでいるが、大都市圏での開催の場合には、公立美術館が会場になることもある。2001年に開始された横浜トリエンナーレは、国際交流基金が主催者に加わり、国の事業として開始されるが、2003年に同基金も独立行政法人化され、さらには2008年開催の第3回展以後、当時の民主党政権による事業仕分けにより、同基金は事業から撤退することになる。しかし、そのことが、横浜美術館が以後、会場としてばかりでなく、その内容に関してもキュレーションに積極的に関わる転機となった。同館館長の逢坂恵美子(美術評論家連盟会員)は、その先頭に立って積極的に企画実現運営に関わりつづけてきた。
2019年8月に発覚した「あいちトリエンナーレ」での「表現の不自由展・その後」をめぐる一連の騒動は、このような芸術祭の展開の流れの中にあるが、会場である愛知県美術館は、そのキュレーター・スタッフが内容に関わっているものの、その根幹を横浜美術館のように最高責任者である館長が先導する構図にはなっておらず、館長の発言が公式に表明されることはなかった。それは多くの展示に関して、「貸会場」的に機能している東京都美術館や国立新美術館と似通った構造が背景に存在するからである。
そのことを批評的に闡明し、議論することなしには、針生一郎が指摘した「美術館批評」が健全に育つことはありえないだろう。そして、そのことを密かに回避しつづけている美術館の基本的な体質を変えることもできないだろう。ということは、今回の騒動は、今後も基本的に潜在しつづけることになる。
雑誌『あいだ』第108号(2004年12月)には黒川典是によるシンポジウムの「傍聴記」が掲載されている。その末尾に「備忘録」として、かつて美術評論家連盟の会長でもあった瀧口修造が、晩年に建築計画中の富山県立近代美術館の館長に慫慂されたときそれを固辞したエピソードが綴られている。この富山県立近代美術館こそ、「表現の不自由展・その後」のもっとも重要な作品の最初のヴァージョンが並べられた会場であった。根本の問題は巧みに回避しようとしても、繰り返し、繰り返し問題として浮上するはずである。いま、シンポジウムを思いだしながら、こころに刻むべきは、その点であろう。