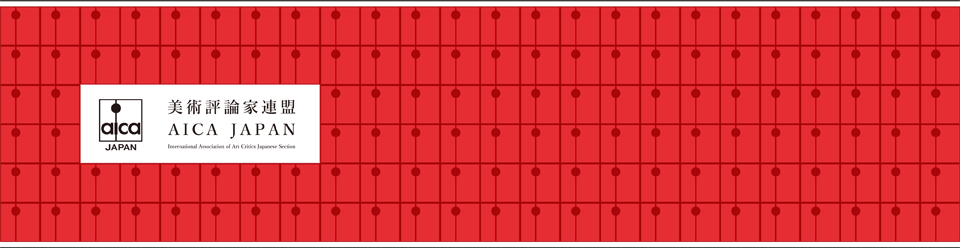批評と場所
尾崎信一郎
聞き手:芦田彩葵
芦田:尾崎さんは、具体美術協会の専門家であると同時に、アメリカを中心とした戦後美術におけるモダニズム理論に精通され、日本の戦後美術を国際的な視野に立って検証されてきました。『絵画論を超えて』(1999)をはじめ多くの批評を執筆される一方で、学芸員として多数の展覧会を企画されています。今回は「批評と場所」をテーマに、場所をキーワードとしたモダニズム美術の相対化、中心と周縁、移動と同時性といった問題について伺います。
具体美術協会(具体)をめぐって
尾崎さんは1954年に阪神間で結成された具体について実証的に研究され、具体再考において重要な役割を果たされました。その方法論として、縦の時間軸、歴史的な接続ではなく、横の空間的広がり、ネットワークという文脈の中で具体を捉えることを提案されています。どのような視点からでしょうか。
尾崎:美術評論家連盟には多くの会員がいらっしゃいますが、私と芦田さんの共通点は美術館の学芸員として批評に関わってきたことです。今回は質問をお受けするにあたって、これまで企画した多くの展覧会における問題意識とも関連させながらお話いたします。
具体美術協会は私の美術批評の原点であり、これまで何度も関連する展覧会を企画し、多くの文章を発表しました。私は大学で美術史学を学び、美術運動や作品を歴史的な文脈において検証することに馴染んでいました。しかしリーダー吉原治良の「誰も見たことのない絵画を描け」という指導を反映した彼らの仕事は参照すべき先例も続く世代への影響もない極めて特異な在り方を示しています。ある時、私は彼らの仕事は時間性ではなく空間性、歴史性ではなく同時性によって説明できるのではないかと気づきました。彼らはミシェル・タピエが唱導するアンフォルメル運動に呼応し、大阪にグタイピナコテカという拠点を設けました。具体とアンフォルメルの関係は同時的、空間的であり、例えばパリのスタドラー画廊、トリノの国際美学センターといった場とともに国際的なアンフォルメルのネットワークを形成し、タピエ自身も57年の来日を含めて世界中を旅行してアンフォルメルを布教しました。そこには歴史性に拘束されることのない新しい美術と美術批評の可能性が兆していたのではないかと考えたのです(*1)。
芦田:具体の活動は、アクションの視点から国際的に注目され、その先駆性が評価される一方で、タピエの要請によって、その活動を絵画にシフトしたとみる意見もあります。パリを中心にアンフォルメル、ニューヨークでは抽象表現主義が展開する状況下で、具体の絵画をどのように位置づけ、評価することができるでしょうか。
尾崎:最初の質問とも関連しますが、抽象表現主義とアンフォルメルの関係は興味深い問題を提起します。抽象表現主義がキュビスムとシュルレアリスムの超克という歴史的な課題への応答であったとするならば、アンフォルメルは歴史との全面的断絶を宣言し、それに代わってヨーロッパにおけるアンフォルメル、アメリカにおける抽象表現主義、日本における具体という世界的な同時性、空間的な広がりをその正統性の根拠としました。アンフォルメルは今日ほとんど顧みられることがありませんが、なぜあれほどの影響力を及ぼしたかについては再検証する必要があります。同様に具体についても、初期のアクションや野外展が注目されがちですが、私はその活動の中心には絵画があったと一貫して主張してきました(*2)。1960年前後の彼らの絵画の豊かさは世界的にも例がありません。ここでは十分に論じる余裕がありませんが、私は以前に企画した「重力」や「痕跡」といった展覧会でその可能性の一端を確認し、具体の絵画についても本格的に検討する論文を準備しているところです。
展覧会と場所
芦田:戦後、ニューヨークを中心に出現した抽象表現主義は、アメリカにも注目すべき美術があることをヨーロッパに知らしめ、美術の中心がパリからニューヨークへ移る契機となりました。尾崎さんも「展覧会の政治学」において(*3)、20世紀美術の展開のなかで展覧会が果たした役割について考察されていますが、1958-9年の巡回展「新しいアメリカ絵画」は、どのような意味をもつものだったのでしょうか。
尾崎:一つの展覧会が世界各地を巡回することが可能となったのは比較的最近であり、ニューヨーク近代美術館(MOMA)のドロシー・ミラーが企画し、ヨーロッパ8都市を巡回した「新しいアメリカ絵画」はその早い例です。抽象表現主義の代表的な作品によって構成され、充実したカタログも制作されました。ヨーロッパの美術界は嘲笑で応えましたが、このような反応は初めから折り込み済みだったと思います。つまりこのような否定によって近代美術を牽引したヨーロッパでさえも理解不能な前衛美術のカッティングエッジ、新しい絵画がアメリカに成立したことが暗示されたのです。私は展覧会が帯びる政治性について何度か論じましたが、アメリカ美術の優越が認知されるにあたって、巡回展という移動、あるいは作品が公開された場所が重要な意味をもったことを示唆するエピソードといえるでしょう。それでは同じ時期に日本で開かれた「世界・今日の美術展」や「新しい絵画世界展」はどうか。この問題は日本人である私たちによる解明を待っています。
芦田:グローバルな視点で美術史を編纂し直すことが進められている現在、モダニズムにおける中心と周縁という捉え方は、どこまで有効でしょうか。グローバルな現代美術展の旗印となったのが、1989年の「大地の魔術師」です。その後、地理的横断に立脚した複数の起源を探る展覧会や、テーマ性によって同時代を捉える展覧会の開催が活発化します。尾崎さんも関わられた1998年の「アウト・オブ・アクション」は(*4)、どのようなものだったのでしょうか。
尾崎:モダニズム美術は前衛に先導されて展開するため、前衛たちが活動した場所を中心として周縁へと伝播していくという発想が成立します。そこには当然、時間的な隔たりが生じますが、興味深いことには周縁や後続が必ずしも中心と先行に劣る訳ではなく、時に注目すべき変容が生じます。私はこのような変容に関心があります。2005年の「アジアのキュビスム」はこのような変容をアジアという地域において検証しましたが、私も2016年に企画した「日本におけるキュビスム」(*5)においてこのような変容が地域のみならず段階的、時間的にも発生することを国内の美術館に収蔵された作品によって検証し、1950年代美術に対する新しい視点を提示しました。
モダニズム美術という発想には明らかに西欧の優越が含意されています。私は未見ですが「大地の魔術師」はかかる意識への批判として構想されたと思います。「アウト・オブ・アクション」 は戦後美術におけるパフォーマンスの系譜を検証する展覧会であり、明らかにグローバルな発想がありました。日本を担当した私のほか、南米や東欧のパフォーマンスに詳しい関係者など、4名の国際コミッティーが美術館の学芸スタッフとともに展覧会の枠組を議論しました。企画したロサンジェルス現代美術館(LA MOCA)のチーフキューレーター(当時)のポール・シンメルには明らかにニューヨークを唯一の中心とみなす美術史観に対するオルタナティヴを提起する意識があったと思います。日本や東欧といった周縁に現代美術の起源を求めるという発想は、1999年にクイーンズ美術館で開かれ、富井玲子さんが日本部門を担当した「グローバル・コンセプチュアリズム」にも認められます。私は2001年にMOMAが企画した東アジアの若手学芸員のためのワークショップに参加した経験がありますが、一方で世界中の美術館スタッフを自らの流儀に合わせて再教育しようというMOMAの帝国主義的な使命感、一方で中心は遍在するというLA MOCAの確信犯的な相対主義、いずれにも世界をリードする美術館の強烈な意志を感じました。
同時性と場所
芦田:尾崎さんは、モダニズム美術理論を批判的に捉えた上で、「重力」展(*6)や「痕跡」展(*7)によって、美術における同時性や場所の問題を新たな文脈で提示されてきました。この二つの展覧会の企画意図や関連性について伺います。
尾崎:展覧会とは作品の選択と配置です。この意味で私はテーマ展こそが一番難度が高く重要であると考えています。「重力」 も「痕跡」もテーマを見つけるまでに数年の時間を要しました。今、おっしゃったとおり、私はモダニズム美術理論を研究してきましたが、展覧会を企画する際にはなぜかモダニズムを批判する作家や作品に関心が向くのです。今回のインタヴューのテーマに戻るならば、どちらの展示も主に日本とアメリカの戦後美術の同時性と関わっています。重力を原理とした作品、インデックス性を重視した作品が日本とアメリカの前衛的な動向の中で同期しますが、それは影響とか模倣ではなく場所を隔てて同時的に発生したのではないか。白髪一雄とルイス、モリスとフォンタナ、一見全く異なる作品の背後に共通の原理を確認することが企画者としての楽しみでした。興味深いことに展覧会自体も同期しています。この二つの展覧会はいずれもポンピドーセンターで開かれた二つの展覧会、96年にロザリンド・クラウスとイヴ=アラン・ボアが企画した「アンフォルム」、そして97年にジョルジュ・ディディ=ユベルマンが企画した「刻印」とそれぞれ問題意識を共有しています。結果的にこれらの批評家にもカタログに寄稿いただきましたが、私がこれらの展覧会の存在を知ったのはいずれも展覧会の企画書をもとに出品交渉を始めた後でした。これもまた一つの同時性といえるでしょう。
ポストコロナと場所
芦田:具体は複数の拠点によって、アメリカ人初のヴェネツィア・ビエンナーレ大賞受賞者であるラウシェンバーグは「移動」によって世界的ネットワークを構築しました。しかし現在、コロナ禍によって、私たちは人との接触や移動を制限されています。展覧会も作品移動に困難が伴い、距離や人流の問題から実際に訪れることが難しい場合が増えています。実体験が希薄となるなかで、展覧会はコレクションや地域性といった場所固有のものへの回帰的傾向があるように思いますが、ポストコロナの批評は、どのようになると思われますか。
尾崎:コロナ禍以後、人や作品の移動が制限され、展覧会を実現するうえでも多くの障害が発生しています。私は今後、美術批評はインターネットや情報を介したグローバルで抽象的な批評と、作品との一度きりの出会いに根拠を置いた現実的な批評に二極化するのではないかと思います。学芸員としての私が拠って立つのはいうまでもなく後者であり、非常に屈折した論理ですが、それは「重力」や「痕跡」同様にモダニズム美術批判としての批評となると思います。
芦田:「場所」をテーマにこれまでの批評についてお話しを伺いましたが、そこには、人の移動が深く関わっていることに改めて気付かされました。抽象表現主義は、アンフォルメルや具体に比べれば、受け身の移動による成立でした。デ・クーニングやロスコのようにヨーロッパから半ば追われた移民第一、第二世代が多かったこと、第二次大戦中にエルンストや モンドリアンなどヨーロッパの前衛芸術家たちが流入し、否応なしに前衛美術の洗礼を受けたこと。だからこそ、それらを乗り越える必要性がありました。ロスコがロンドンにあるテートにおいて、ターナーの横に「ロスコ・ルーム」が設置されることに執着したのも、この複雑な心情からの強い場所性へのこだわりからではないでしょうか。
また中心と周縁、先行と後続といった場所や時間の問題に拘わらず、接触や衝突のなかで美術表現として豊かな変容が生まれているというご指摘は、今後非西洋の美術がグローバルな視点で検証されていく過程で一層重要になると思います。その一方で、アジアの国立美術館を中心にナショナル・アート・ヒストリーに基づく展示が重視され国家間の競争も垣間見えることから、国際性と地域性の両方の視点からなる批評がさらに活発になると思います。
コロナ以後の批評の二極化のご指摘については、鑑賞体験との相対関係のなかで展開されると思いますが、今後どのようなモダニズム美術批判としての批評を尾崎さんがお書きになるのか、読ませていただくのを楽しみにしています。
(*1)尾崎信一郎、基調報告「グタイピナコテカあるいは60年代のグローバリズム」『野生の近代 再考―戦後日本美術史 記録集』国立国際美術館、2006年、210-260頁。
(*2)一例として以下を参照。尾崎信一郎「具体 絵画へいたるアクション」『具体資料集 ドキュメント具体1954-1972』芦屋市立美術博物館、1993年、11-17頁。
(*3)尾崎信一郎「展覧会の政治学-ミニマル・アートをめぐる3つの展覧会」『西洋美術史研究』No.10、2004年、94-107頁。
(*4)Out of Actions: Between Performance and the Object, 1949-1979, The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, Feb 8,-May 10, 1998. 翌年、東京都現代美術館に巡回した。
(*5)「日本におけるキュビスム-ピカソ・インパクト」展(鳥取県立博物館他巡回、2016-17年)は、キュビスムが日本において別々の文脈で2度にわたり受容されたという仮説のもと、ピカソらの作品に触発された日本画家の作品約160点により状況を検証した展覧会。
(*6)「重力 戦後美術の座標軸」(国立国際美術館、大阪、1997年10月30日-12月9日)は、抽象表現主義、アンチフォーム、アースワーク、具体、もの派など戦後のアメリカと日本の現代美術の展開を重力との関連から検証した展覧会。
(*7)「痕跡-戦後美術における身体と思考」(京都国立近代美術館、2004年11月9日-12月19日)は、作品に表れる作家の痕跡を起点に、抽象表現主義、ウィーン・アクショニズムやコンセプチュアル・アート、具体、読売アンデパンダン展の周辺作家といった欧米および日本の戦後美術の様々な動向を検証した展覧会。