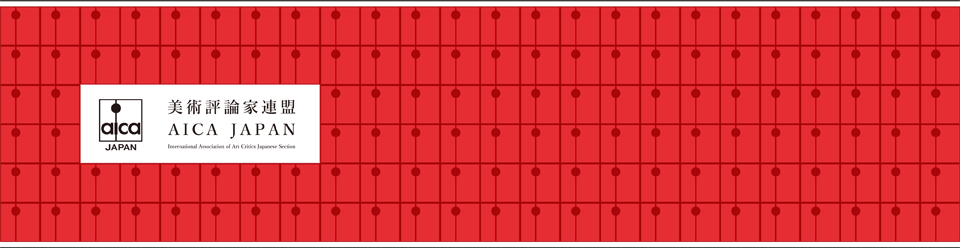「批評と対談」
早見堯
聞き手:佐原しおり
佐原:数年前、1978年11月の『みずゑ』に掲載された榎倉康二さんとの対談について、早見さんに質問させていただいたことがありました(*1)。当時、私は榎倉さんの平面作品に関する論考を書いていたのですが、榎倉さんの1970年代後半以降の作品変遷を読み解くうえで、この対談は非常に重要であると感じました。今回はこの対談について、改めてお話を伺いたいと思います。
この対談は「現代との対話」という連載の一部でした。まずは連載「現代との対話」について質問させてください。この連載は『みずゑ』1978年6月号に第1回目が掲載され、早見さんは1979年6月まで13回にわたって担当されていました。対談相手は、菅木志雄、辰野登恵子、柏原えつとむ、岩本拓郎、山田正亮、榎倉康二、原口典之、松本陽子、堀浩哉、清水誠一、高木修、諏訪直樹、彦坂尚嘉(敬称略、掲載順)と錚々たる顔ぶれでした。この対談を担当されたきっかけは何だったのでしょうか。
早見:『美術手帖』に初めて依頼原稿を書いたのはたしか1974年、福住治夫さんが編集長のころ、1年間の総括ということで、宮川淳が好きだったので引用の織物風なドキュメントでした。多分、藤枝晃雄さんの働きかけだと思います。とりあえず書かせてみようということだったのでしょうね。その後、1年間「美術時評」でいろいろな評論を取りあげました。「美術時評」が、おそらくきっかけで、高階秀爾さんに頼まれて『季刊藝術』に展覧会評を書くようになりました。というような前提があって、『美術手帖』1978年1月号「創刊30周年記念特集 」の「未完なるものの過程から」に「ヌーボ・レアリスム論」を頼まれたのです。これは、わたしとしては、今となっては恥ずかしい部分もありますが、2日間寝ないで書いたので「力作」だと思ってます。そういう経緯で、ここでも藤枝さんの働きかけがあったのではないかと思うのですが、「現代との対話」を頼まれました。今は錚々たるメンバーですが、当時はそれほどではないです。不得手な作家と得意な作家とはっきり二種類で、椎名節さんがアレンジしました。得意な作家は辰野登恵子、岩本拓郎、山田正亮、原口典之、松本陽子、清水誠一、高木修ですが、他の作家は当時苦手でした。
佐原:「現代との対話」の連載は見開き4ページほどで、どの回も非常に密度の高い内容でした。本来であれば各回について細かくお話を伺ってみたいのですが、今回は榎倉康二との対談に絞りたいと思います。早見さんは『みずゑ』での対談以前に、『美術手帖』の展評や、「特集 絵画と平面の相克」に寄せた論考のなかで何度か榎倉さんの作品に触れられていますが、当時の榎倉さんの作品をどのようにご覧になっていましたか。
早見:当時の考えを思いだしても、大森荘藏がいうように記憶は現在再生産されるわけなので、大半は今の考えなので、正確に当時の考えとは言えないのですが、当時は、批評の立脚点をはっきりさせるために、賛成か反対か硬直した二者択一的態度だったのでしょうね。ある作家のある作品を良いと思っても、自分の批評の立脚点から「意義あり!」と全共闘みたいに、ある意味で自己批判していたわけです。ツッパッてたというか、自分で自分の批評の立脚点をわかるためという方が正確かも。榎倉さんの作品はとても意義深いものだと思うのですが、認めたくないというような気持ちもあるわけです。原口さんの場合なども、1977年のカッセルのドクメンタの作品は最高だと思います。同じ年のパリビエンナーレのオイルプールの上に鉄板を吊り下げた作品は良くないです。でも、以前から知っていてとても好きな作家です。作品集を出すからと評論を頼まれて、そこでわざわざ批判する文を書いてボツにされ、当分の間、口を聞いてもらえない状態だったりというようなこともありました。賛成の反対は反対の賛成なのだとかで、どうなってるのかわたし自身もわからないので、文の行間を読んでもらいたいですが。原口さんとはその後仲良くなりました。
佐原:榎倉さんは1970年の東京ビエンナーレで展示した《場》に代表されるように、油や水などの液体の浸透や、物質同士あるいは空間と肉体の接触を、緊張感のあるかたちで切り取った作品が評価されてきました。対談が行われた1978年以前の展評や論考を読んでみると、そういった「直接性」が評価の主軸となっているように見えます(*2)。そしてこれは現在でもあまり変わっていないのではないでしょうか。対談のなかで早見さんはこの要素をむしろ批判的に捉えていたのが印象的でした。このような視点を持つようになったきっかけがあったのでしょうか。
早見:その「直接性」を批判的に考えていました。「ヌーボ・レアリスム論」でもそうなのですが、「媒介性」を失った「直接性」は生 の物質や物体の状態と同じではないかと考えていたのです。榎倉さんはそういう制度化された「媒介性」を克服するための身体性や物質性だったわけです。媒介性というのは、絵画や彫刻ということもありますが、描いたり作ったりするプロセスや身体性、表現の過程ということでもあります。それが欠けていると現実そのものを見ている状態に近づいていくので、何らかの媒介性をもった「作品」を「見る」という充実した時間が失われてしまうのではないかと思っていたのでしょうね。
佐原:当時は絵画と平面の問題が盛んに取り上げられており、榎倉さんも1978年前後を境にカンヴァス作品を多く手掛けるようになっていきます。対談のなかで榎倉さんは、自身を「描くことの代償として物を使う人」として位置付けつつも、物質的な接触や出来事性といったこれまでの関心を継続させることと、「描く」という行為の両立の難しさを吐露しているように見えました。早見さんはそういったところに、まさに丁々発止という感じで厳しく切り込みながら質問をされていました。当時の榎倉さんのこういった問題意識に対して、早見さんはどのような考えをもたれていましたか。また対談を通じた榎倉さんの印象はどのようなものでしたか。
早見:「平面としての絵画、絵画としての平面(*3)」ですね。わたしは1976年から77年パリに滞在して、シュポール/シュルファス系列のルイ・カーンやステイン技法のマルク・ドゥヴァドなどの活動を多少聞きかじったり、カトリーヌ・ミレーが編集長の「art press」をめくったり、ジャン・クレールの、 1972年だと思うのですが「パンチュール(絵画)はテンチュール(染め物)になった」 というフレーズに感心していたので、榎倉さんの「浸透」は彼がパリにいるときにこのあたりに関心をもったのだろうと推測していました。対談に関しては、当時、わたしにとって榎倉さんは高山登さんと同じように、わたしと一、二歳しか年齢は違わないですが、大関と幕下みたいな関係だと認識していました。ある意味言いたい放題にわたしが喋って、榎倉さんが正面から受け止めてくれたという感じでした。作家は制作を通して思考してるんだ、オトナだなあと実感しました。
その後の、1980年の原美術館のハラ・アニュアル(*4)の榎倉さんの作品は素晴らしいなあと思いました。壁に張られたキャンバス布が2枚交差し、交差した部分が浸透していて、一枚は床に垂れていました。枠にはるとか壁に掛けるという絵画の約束事を脱臼して物体の状態が強調されていながら、しかも物質の出来事が制作のプロセスになっているところが、視覚性を超えた物質性や時間性を切り開いていると思ったのです。
佐原:この対談が行われた当時、榎倉さんは廃油と木材と綿布を使用しているのですが、この後から油彩やアクリル絵具を使うようになっていきます。早見さんがおっしゃったハラ・アニュアルの作品も、油彩によるものでした。早見さんとの対談のなかで、榎倉さんは「たとえばいま材料として廃油を使っているんだけど、その材料でも乗り越えたいと思うわけ。絵具にしたら、描くという行為とは違うかもしれないけれども、それに近い行為ができるんですよ。いま材料を研究してるんです(*5)」と話しています。この対談以降、榎倉さんの文章の中に画材の話が時々出てくるようになるので、私はこのあたりの変化にとても興味を持ちました。取材時でも、それ以外の場面でも良いのですが、榎倉さんと画材に関する話をされたことはありますか?あるいは、榎倉さんの使う材料の変化について、何か覚えていらっしゃることがあれば教えてください。
早見: 材料について榎倉さんと話したことはありません。ただ、材料とリアルタイムでやりとりというか対話しながら制作していくという傾向がより強くなっていったのだと思います。作家はあまり自分が使っている材料について普段は特に何も言いませんね。たとえば、もっと前ですが、「点」展で榎倉さんのアトリエを訪れて、水道のホースを庭の柿の木に沿わせた作品を榎倉さんと田窪恭二さんと一緒にアトリエから眺めながら話したことがあるのですが、特に複雑な話をした記憶はないです。ふと思ったのですが、「浸透」というコンセプトではイヴ・クラインと似ているところがあるような気がします。イヴ・クラインは「浸透」をコンセプトにして火や水、空気、絵具、さらに自分の身体まで材料にして作品を作ったわけですが、ある意味でどんな材料でも使いこなせる可能性があったと思います。榎倉さんも同じだったのではないでしょうか。
佐原:対談の中でお二人がざっくばらんに話されているので、当時から榎倉さんと交流があったのだろうと勝手に想像していました。今回お話を伺って、早見さんは榎倉さんの作品を批判的な立場で見ていらしたからこそ、繰り返し質問を重ねることで、作家自身の考えや逡巡を引き出されていたのだと思いました。作家や作品を評価しているから、良い批評が書ける、良いキュレーションができる、という考えもあるとは思うのですが、評価する/しないという軸とは別に、わかったつもりにならずに対象と向き合う姿勢のお手本を見せていただいた気がします。素晴らしい対談がうまれた経緯を知り、とても興味深く、また勇気づけられました。ありがとうございました。
(*1)「現代との対話−6 榎倉康二+早見堯 出来事としての絵画について」『みずゑ』1978年11月、pp.84-91
(*2)早見氏は、対談の導入文において「かつては作品を作り上げていた、対象や素材や材料(道具)、作る過程(手段)という媒介性が、即作品とされている。このような、道具や手段、-したがって物体性や身体性をそのまま作品として提示する。無媒介の直接性は、現今の美術を一面で特徴付けている」(同上、p.84)と説明している。
(*3)「特集 絵画の平面と平面の絵画」『美術手帖』1977年4月、pp.1-115
(*4)「第1回ハラ・アニュアル 80年代への展望」原美術館、1980年
(*5)*1、p.86