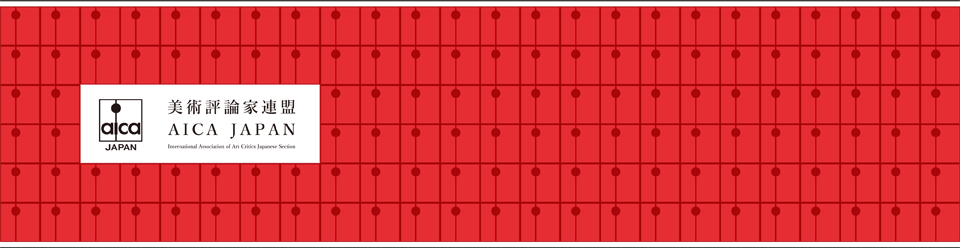古き良き画廊物語の終焉
藤田一人
2021年春、東京・湯島の老舗画廊、羽黒洞木村東介が閉廊した。長く付き合ってきた私にとって、それはあまりに急な出来事だった。しかし、思えば昨年は銀座のフジヰ画廊が閉廊する等、業界で名の通った画廊が次々に姿を消している。コロナ禍は日本の美術界にも少なからぬ影響を与えているということなのだろう。
羽黒洞木村東介は、先代の木村東介(1901―92年)氏が民藝を扱う古美術商として「羽黒洞」を創業。1936年に東京の湯島天神上に店舗を構え、70年には湯島ハイタウンに画廊を開設。先代亡き後、屋号を改めた。
東介氏は昭和の名物美術商。右翼運動の後、柳宗悦の民藝運動に刺激を受けて美術商に転身。郷里・山形の民芸品に始まり、長谷川利行、中村正義、そして肉筆浮世絵等、それまで売れ筋ではなかった作家達や作品を市場に押し上げ、定着させることで、美術界に名を馳せた。その商売スタイルは業界内では異端児扱いされたが、私には実に正当に思えた。彼の一貫した姿勢は、既存の価値観に頼らずに新たな価値を生みだして美術品を売る。そのためには、まずはこれだと決めたものを徹底的に買うことで商品の数を確保し、価格設定の主導権を握り流通をコントロールする。そして商品の知名度を高めるために積極的な宣伝活動を展開する。また、売れていようがいまいが、現存作家の面倒をよく見た。それが後の財産となるからだ。まさに市場形成の王道と言えるのだが、昔も今もそれを実践する美術商は稀だ。
そんな東介氏の跡を継いだのが長女の木村品子さん。父の遺産(大量の在庫を含め)を背負う葛藤と経営の苦労は並大抵ではなかっただろう。父とは違い、品子さんは非常に気のいいお嬢さん。その朗らかな気質が画廊を和やかにし、多くの人々が集った。彼女はいつでも顧客や作家をもてなして、楽しい気分にさせる。画廊とは単に美術品を鑑賞し、売買する場ではなく、訪れた人々が一時を楽しんで、豊かな気持ちになる場だという思いがあったのだろう。私はそんな品子さんに甘えて、作家や顧客たちと激しく議論し、酒を呑んでワイワイと騒ぐのも度々だった。
そうした人間のふれ合いと商売の躍動を併せ持った画廊物語は、もはや今は昔としみじみ思う。