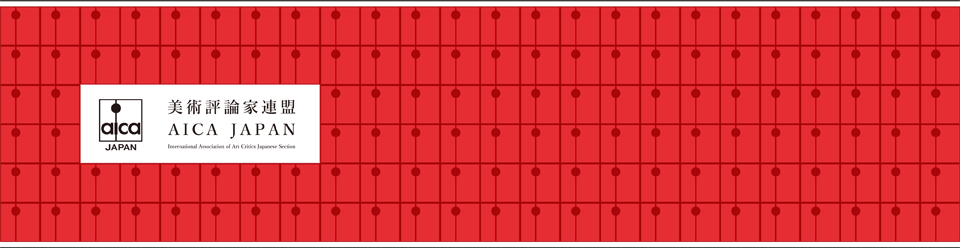美術評論の生態系
四方幸子×アンドリュー・マークル
アンドリュー・マークル(以下AM) 今年、四方会長と会員の有志と共に、国際関係・若手育成のワーキング・グループというのを立ち上げたところです。美術評論家連盟はそもそも、国際的なものとして設立されています。つまり、美術評論家連盟の存立基盤に国際性があるはずです。転じて、近年の日本の社会情勢や美術のあり方を見ると、国際性とは逆の閉鎖性へと進んでしまっているように思います。海外の大規模国際展を見ても、日本の作家が参加していない、もしくは参加していたとしてもその展覧会のコアな議論に含まれていなくて、アウトサイダー的な立ち位置になりがちです。また、 『Artforum』であれ、『October』や『Afterall』であれ、『e-flux journal』であれ、国際的な言論を形成する雑誌は日本の評論家による寄稿がほとんどなく、日本の問題意識が世界的に流通していないことにもどかしさを感じています。私はここで、グローバルだから価値があると言いたいわけではありません。しかし、それを言い訳にするのも良くないと思います。グローバリズムとローカリズムの複雑な連関こそが問題です。
そこで質問なのですが、四方さんは美術評論家連盟・日本支部の会長になられて、日本とインターナショナルなものとの関係性をどのように捉えていらっしゃいますか?
四方幸子(以下 四方) まずそれが近年のことなのか、そもそもそうだったのかという点があります。もちろん、ここ数年で日本経済が悪化しており、それにコロナが重なったことで急激に内向きになっているとは言えると思います。日本の世界的なプレゼンスが下がっている。海外に向かう留学生の数も激減していますよね。そこで二つの原因が考えられると思います。一つ目ですが、日本のアーティストはそれぞれが切実な問題と格闘していると感じていますが、グローバルな文脈の中での社会・政治性と向き合っている例は多くないように思います。議論の土台にうまくアクセスできていない。もう一つは、世界の側から日本の美術に期待されているものとの齟齬があるのではないでしょうか。欧米視点のフィルターがかかったものが求められており、それに対して日本のアーティストが表層的に応えてしまう場合もあると思うんです。例えば、欧米の表現に沿わせたり、逆に日本のサブカル的なものを打ち出したりと。簡単ではないと思いますが、自分たちのもつリアリティの深層に徹底的かつ継続的に向き合い、それによってローカルな問題をグローバルな俎上に載せていくのが重要だと個人的には思っています。欧米中心的な価値観や傾向に寄せるのではなく、地に足をつけてそこと対峙できるような方向に進む道があるはずです。
美術評論にも同じことが言えます。日本語をベースとしていて、海外の評論家との交流・交換が活発とはいえないですよね。これまで「国際派」だった評論家は、欧米で起きていることを日本に「紹介する」という役割を担っていた人が多い。そこから日本の固有性へとフィードバックする志向がかつてはあったと思うんです。現在は、誰もが海外から情報を得ることも海外に発信することもできますし、以前とは比較にならないほど多面的な分析や批評が可能な時代になっている。なのにそういう動きはほとんどなされていない。日本の美術評論家連盟は、海外の支部との交流もほとんどないですし、批評的な問題を一緒に考えていくような動きがないという状況が続いています。わたし自身は会長として会員の皆さんと一緒にこの問題を改善できないかと考えています。
AM グローバルになるためにはローカルな知見を蓄積しなければいけない。この点は賛成です。海外の美術館で日本の美術が取り上げられるときは、戦後美術に焦点をあてたものが多い。しかし、他の歴史的な流れ、あるいはいままさに起こっていることについてはあまりフィーチャーされない。海外発信としてパッケージした「日本」あるいは「日本的なもの」ばかりをネタにするのではなく、日本国内の議論を活性化させれば、海外の動向とシンクロできる回路がひらくと思います。
四方 日本語の問題があると言われています。私自身は、英語の原稿を依頼された時、自分で行う、翻訳者に頼む、機械翻訳で済ませる、を使い分けています。精度の問題はあるものの、機械翻訳が出てきたことで以前よりも翻訳に関わるハードルは下がっていますよね。ですので、翻訳の困難は少し言い訳ではないかと思っていて、むしろマインドが固定化されているほうが問題です。ドメスティックな心性を変えていかなければならない。
グローバルというのは、美術においてはまだまだ欧米中心主義を意味しています。それに従うか抗するかの二分法になってしまう。しかし、グローバルは多文化に対して開かれたものであると想定できると思うんです。ハイブリッドに、複合的に連結されていくような世界観を構想できないでしょうか。文化的にも日本は、明治以降に急速に近代化を進めたことで、アジアでありながら欧米のフィルターをもつという中間的な位置にあって、アジアや他の非欧米地域と比べてうまく発信しづらい。でも、逆に蝶番としての可能性を豊富にもっているとも考えられます。グローバルを再解釈して発信するようなことができるといいですよね。
AM ウェブ3.0の時代に日本が内向化していることが不思議に思うんです。SNSなどコミュニケーション・ツールが発達しています。ヒエラルキーのある構造ではなく、「点から点を結ぶ」ネットワーキングが可能になっています。
四方 日本語で日本人だけがわかりそうな内輪的な使用をしてしまいますよね。親密さに浸ってしまうような。ただ最近は、Discordなどで趣味から世界と繋がる人も増えていると思います。そこに期待していますが、そういったことが美術評論の中ではいまだに起こっていない。
AM 四方さんが美評連の会長になられてから積極的に他の部門、とりわけアジア=パシフィック地域の部門と連携するように努められていますね。
四方 今後、アジアでのネットワーキングを充実させていくことを考えています。香港や台湾とはすでにコンタクトを取っています。少しずつ始めて、パリを中心とした国際美術評論家連盟に対して、いずれはアジアからも発信していきたいと。国際美術評論家連盟はもともと、第二次大戦後にユネスコが中心となって誕生しています。西側・欧米の主導でスタートしていることに自覚的になるべきでしょう。その上で、国際美術評論家連盟全体をボトムアップからグローバルにしていくことを目指したいんです。
AM 私も賛成です。四方さんは日本における美術評論の現状をどのようにお考えですか。
四方 とにかく美術評論の媒体がとても少ないですよね。各地域でもいろいろなメディアが登場することを期待しています。60年代くらいまでは地方にも様々な活動があり、同人誌などを通して議論が活発だったと思います。それがいつの間にか東京中心の状況に回収されてしまっている。その背景には、現代美術がヴェネチア・ビエンナーレやドクメンタなどに代表される大規模国際展やアートフェアというグローバルな動向に左右されるようになった80年代があります。その大きな転換が、日本の地域的な固有性を消してしまう方向に働いたのではないでしょうか。
AM 従来の雑誌であれば、編集部がコンテンツに対する権力をもっていました。それによってある種の可視性が評論に付与されていました。しかし、現在のウェブ状況では誰でも発信できるがゆえに、個々の言説が逆に見えなくなっています。誰かがそれを集約する必要があるのだけれど、それをやってしまうとまた権力がそこに集中してしまう。まあ、グーグルがその典型としてあげられるのでしょうが、可視性と権威性のジレンマがあると思っています。
四方 グーグルなどメガ企業によるサービスは便利であるとともにゆるやかな権力として日常に偏在している。そのことを念頭に置きながら、編集や情報のキュレーションを行うことが美術評論においても必要だと思いますね。そもそも商業的ニーズがあまり高くないものですから、それを逆手にとって新しい媒体を構想することもできるんじゃないでしょうか。今後ウェブ3.0の時代に移行していけば、自立分散型でインタラクティブな編集や出版、収益のあり方が生まれるかもしれません。
AM 戦後の『美術手帖』を調査したのですが、山口勝弘や李禹煥、菅木志雄などアーティストが雑誌に積極的に介入しています。御三家と呼ばれる東野芳明、中原佑介、針生一郎以外にもヨシダ・ヨシエなど面白い評論家が活躍していました。しかし近年の日本の美術メディアでは、そういった充実した企画がなかなか見当たりません。
四方 先ほどウェブ3.0と言いましたが、デジタルでの発信が増えることで、時代の趨勢とはいえ紙媒体が激減していることを危惧しています。と同時に紙の重要性が増しているようにも思います。インターネットによって責任の概念が希薄になりました。しっかりと責任をもって何かに向き合い、発信し、吟味する場があまりない。さらに、山口勝弘さんもヨシダ・ヨシエさんも極めて領域横断的な方たちでした。時代背景は異なりますが、より広い視点で美術を捉える眼を持っていたように思えます。60-70年代の横断性を、現代においてどのように再接続できるかは課題ですね。インターネットが普及した現代では、内輪の論理に向かうのではなく、書き手にも読み手にも開かれた美術評論を目指せるのではないでしょうか。時代の変化に自覚的に向き合い、積極的な発信を行うと同時に、美術界以外の書き手を含めたより開かれた美術評論の可能性を開いていきたいですね。評論による新しい生態系を作っていけないかと思っているんです。
AM いま、60-70年代とおっしゃいましたが、私は1920年代の、戦間期の前衛も示唆的だと思います。海外から輸入された様式だと1990年代以降に台頭した「日本現代美術」の歴史から排除されてきたものですが、村山知義が提唱していた〈意識的構成主義〉やプロレタリア美術運動などは欧米・ソ連各国の芸術動向とリアルタイムでリンクしていて、かつそれを日本に落とし込む実践方法も優れていました。社会的・政治的な活動でもあり、また領域横断的でもありました。なによりも非常に強いミッションや切迫感のようなものが原動力となっています。
四方 1920年代や戦間期など、非常に強い外圧に晒されていた時代は、そのような原理が駆動しやすかったでしょう。しかし、いまの社会は格段に複雑化し、権力構造も入り組んでいるためそう簡単ではないと思います。誰もが多面的存在であり、被害者や加害者の複数の側面を持つ当事者としてある。そのような前提で複数のオリジンから情報を得て、トピックを選び取り発信するようなキュラトリアルな方法になる。
書きたいこと、書くべきことは多様にあると思うんです。一人の人間の中で収拾がつかないようなことだってあります。社会は混迷の中にありますが、美術も同様です。科学・技術や経済の影響も強く受けています。例えばNFTによって作品やオリジナリティの概念が大きく揺さぶられている。美術評論ひいては美術全般において、未曾有の事態が現在進行しているとも言えます。ただ書くべきことがありすぎて、それらをまとめ上げることが困難になっている。過去のように外圧によるリアクションではなくて、湧き出る能動性を立ち上げないと批評は駆動しないのではないでしょうか。問題意識を発掘し、対象を定め、方法を吟味する。実際、多くのアーティストはそうやって作品を制作していますし、評論家もそうする必要があるのではと思うんです。
AM 評論家はもっとアーティストのようにならなければならないということでしょうか。
四方 社会は劇的に変動しているし、それによって美術も変容し拡張しています。美術評論もそれに沿って変わっていかなければならないでしょう。またアーティストとキュレーター、評論家の境界も、かつてないほど狭まってきているのではないでしょうか。実際これら複数の活動を並行して行う人も増えてきています。
AM いま仰った社会の変動の中で一つあげられるのは、ジェンダーの問題です。美術評論家連盟はそれを受けてどう展開するのでしょうか。
四方 いま、美術評論家連盟の女性会員は25%ほどです。その中で、20人の常任委員は半数以上が女性なんです。これからはいっそう男女のバランスが取れていくことを期待しています。美術界に限りませんが、私が社会に出た頃は、女性は今よりも補助的な役割をすることが多くありました。そのような中、私は自分のビジョンをもち活動する先輩女性に出会う機会に恵まれました。日本人では、和多利志津子さんや道下匡子さん、湯川れい子さんなどです。道下さんは、グロリア・スタイネムを始めとするフェミニズム運動に近しい方でした。キュレーターやライターの分野では徐々に女性が増えてきましたが、館長職が増えたのはここ数年です。大学では2000年から授業を持っていますが、ここ数年で女性が増えてきたものの大多数が男性教員です。近年は美術界でも男女を含め様々な格差や分断に対して当事者が声を上げることで、オープンに検討する状況になってきましたね。今後数年で、ますます変化するのではないでしょうか。
AM 私は2020年—2021年に、文化庁アートプラットフォーム事業の翻訳事業のファウンディング・エディトリアル・ディレクターを努め、選書チームの一員でした。翻訳する意義があると思う文献や記事を調査して、それを読んでチームで話し合って選んでいくというプロセスを踏んでいます。そこでもジェンダーバランスは議論になりました。例えば、戦後の日本の美術評論のベストを選定しようとすると、どうしても東野、中原、針生やその周辺がいて、となって、トップ10が全て男性になってしまうこともありえます。現在そして未来の評論に繋げるという意味ではとても問題含みのセレクションになってしまうんです。最終的に「日本のアートとフェミニズム」や「コレクティヴィズム」など、いくつかのテーマを枠にして、各テーマの選定においてできるだけジェンダーバランスを念頭にするような体制を取り入れました。それでも10本のうち3本が女性の著者に留まるぐらい、厳しい状況になっています。
四方 美術においては男性中心主義と近代主義、西洋中心主義が絡まり合いながら発展してきた歴史がありますよね。そして日本では、明治以降もともと持っていた文化をいったん横に置いて、西洋美術を拙速に輸入することで美術を成立させてきた。西洋美術、そしてそれを受容した日本の美術における近代や男性中心主義を再考し、解きほぐしていく時代になっている。その作業は、美術と共働しつつ美術評論が担えるはずです。
AM その通りですね。ジェンダー問題というのは、PC(ポリティカル・コレクトネス)だけではなく、我々がいかに歴史を批評的に再考できるかという契機となりうるものです。
四方 内面化されていて気づかれない状態はとうに超えている現状があります。女性やマイノリティの声が見えるようになってきています。それに対するバックラッシュも美術業界で起こっている。今年のヴェネチア・ビエンナーレの企画展「The Milk of Dreams」では、90%以上が女性かノンバイナリーの作品でした。そこにはエスニック・マイノリティたちの作品も多く含まれていました。それに対して、逆差別であるという声があがっていると聞きました。パーセンテージの問題というよりも、過去をどのように捉え直したかの方に目を向けるべきだと思うんです。過去を再考した結果としてのパーセンテージであって、内実は歴史理解の方法の側にあるのではないでしょうか。今年のドクメンタも含めて、どうしてもバックラッシュが起こってしまう。男性などマジョリティの側にいる人の不安をかき立ててしまう。でも、作家や評論家はそもそも複数の視点で世界を見ることができる人たちのはずです。狭い見方を変容させる力が美術にはあるわけで、その良さをいかに伝えていくかですよね。美術というのはアクチュアルな学びの場なんです。時間をかけてでも美術を機能させていくことが必要です。そうしないと、何も問題が解決していかない。いつまでたっても縄張り争いのようなことが劣化しながら進行していく。ちょっと極論かもしれませんが。
AM 「The Milk of Dreams」が参照している文献の一つに、アシュラ・K・ル=グウィンの「The Carrier Bag Theory of Fiction」(邦訳は「小説 ずた袋理論」篠目清美訳『世界の果てでダンス ル=グウィン評論集』白水社)というテクストがありますね。それが展覧会の重要な部分を構成していました。そこでは男性中心主義的なものとして、例えば原始社会におけるマンモス狩りといったものを脱構築するようなヴィジョンが提示されていました。マンモス狩りを行うには槍が必要ですが、そもそもそれに先行して石や木、紐にするツタなどの物を集める作業が必要だったことが強調されます。そうすると、人間にとって本質的な道具とは槍ではなく、カバンなんだと述べられます。種や石などあらゆる有用なものを運ぶための籠やカバンですね。狩りhuntの前提には運ぶことcarryがあった。勇敢な出来事が生まれない日常行為の集積に着目することで、男性中心的なものとは違うフィクションが生成するのではないかという、すごく面白いテクストなんです。ル=グウィンのように、新たなストーリーのあり方を探して提示することは重要です。
四方 物事のバックボーンを探求し、目を向けることで、はじめて物事そのものに向き合うことができる。そういう間接的な作用でもって美術は機能する。見えない部分を感知し、世界を関係において可視化できるのが美術の特質ですよね。
AM少し話をかえますが、四方さんはメディアアートの専門家でいらっしゃいます。いまのメディアアートの状況をどのように分析されていますか。
四方 難しいですね(笑)。私が関わり始めた90年代は、領域横断的な実験が探求された時代で非常に刺激的でした。しかし、いまは経済に紐づいたものが多くなっています。良くも悪くも一般に普及し、エンタテインメントとして消費されてしまっている。メディウムというものを根源的に問うような作品が少なくなっています。私個人はむしろ創造的かつ批評的なハッキングや状況への介入を期待しています。作品と環境がダイナミックに変わっていくような、オープンなプロセスや解釈を許容するものに魅力を感じてきたのですが、最近は、作品との表面的なインタラクションに体験が縮減されがちのように思います。
加えて、科学・技術の発達があまりにも早い。AIやバイオテクノロジーは倫理的な問題を突きつけています。そういった動向を踏まえつつ、コラボレーションや対話を通して生まれるプロジェクトが重要だと考えています。
AM 90年代のNTTインターコミュニケーション・センター[ICC]や四方さんの関わっていたキヤノン・アートラボなどの活動は非常に画期的なものだったと思います。最近、メディアアートというジャンルが固まってしまっている印象を受けます。
四方 現代美術でも新しい技術を使う作家は増えています。メディウムに対する省察性を備えた側面から見ると、メディアアートと現代美術の垣根がなくなり始めているかもしれません。しかし前者が科学や技術の潜在的可能性からアートに挑むのに対して、後者はその逆のアプローチを取っていると現時点では思います。
それ以上に大きなフレームで見ると、やはり科学・技術の発展のスピードが非常に早いんですね。よく言われるのは、90年代はコンセプトに技術が追いついていなかったけれどいまは逆で、科学技術にコンセプトが追いついていない。さらに言えば、新しいコンセプトと技術を合致させられるような人は、例えばすでにグーグル社に雇用されていたりします。メディアアートは現代美術との対比で語られることが多いのですが、それよりも、大企業でなされる技術開発に対してDIY的になされる技術開発があって、どちらも美的な次元や倫理的な問題を含んでいるものの、これらの対比の方が重要かもしれません。個人的にはDIY的なネットワークを重視していますが、メディアアーティストがもっと企業や研究機関とコラボレーションをする道があっても良いと思います。困難な側面があるとは思いますが、相互触発することで未来の社会や創造を開く可能性があるのではと。DIYでも組織でも、トライアル・アンド・エラーを許容できるような場所があってほしいと思います。
AM 美評連に話を戻します。美評連の会員の半分近くは、美術館で働く学芸員か大学の研究者です。私自身はフリーのアートライター、評論家としてやっています。しかし、生活のためには編集や翻訳の仕事をせざるを得ない。そうなると忙しくてなかなか展覧会を見に行けないんですね。美評連の中でもフリーの人はみんなそういう状況だと思います。非常に厳しい状況だと思うんです。その中で、アクチュアルな評論の場はどのように可能となるでしょうか。
四方 私もフリーランスなんですが、実際100%評論だけで生きていくのは難しく、それが良いとも思えないんです。とはいえ日本の美術界は、一部のギャラリー以外は20-30年前と較べても予算規模が格段に縮小し、美術に関わるだけで疲弊している状況が深刻化しています。美術関係者のユニオンも生まれていますが、アーティストや評論家を含め、美術に関わる様々な人々がそれぞれ声を上げていく時期にあるように思います。その上で、評論に加えてキュレーションや編集などを同時並行で行うのは、現代において自然なことだと思うんです。若い世代では、そのようなスタンスで活動している人が増えています。複数の側面を持つとバックアップにもなりますし、それぞれの経験やネットワークを生かすこともできる。
美術が拡張している以上、評論も拡張していくと先ほど言いましたが、評論も、文字、映像、シンポジウムやトークイベントなど、多様なかたちで展開が可能ではないでしょうか。さらに言えば、アーティストであれば生きていること自体がアートだという例がたくさんありますよね。評論家も生きていること自体が批評行為であると言えるところまで持っていけるのではないでしょうか。それは何も、求道的に難しいことをしろと言っているのではなくて、軽やかに要所要所で種を蒔き、それらが育って生態系を作っていくような方法があると思うんです。オンライン環境によってそれがやりやすくなっているとも思います。
AM ただそうすると、距離を置いて客観的に物事を把握し反省する、従来の評論家のあり方がなくなってしまう懸念があります。キュレーターは、どうしてもギャラリーや作家と相互依存して仕事をしています。そうすると厳しい視点の評論は書きづらくなってしまう。私の場合も翻訳で作家と仕事をしたりしているので、そういう状況があります。評論の多面的展開は、実際はいろいろな絡み合いによって客観的な評論ができないことと裏表の関係にあるんじゃないでしょうか。
四方 客観的な評論のあり方、重要ですね。と同時に、動的に移動しながら思考するような評論が並存していく時期にあるのではと思います。対象と距離を置く客観的な評論は近代において成立し、机上が思索や執筆の場所となっていました。そのような中、ベンヤミンは約100年前にパリのパサージュを徘徊する中で、当事者としての独自の思考を断片的なテキストとして生み出しました。現代私たちは、スマホなどモバイル機器をもち、様々な場所で撮影しテキストを発信し、配信さえも可能になっている。紙媒体が新たな重要性を帯びているのと同じように、評論のあり方が拡張する中で、近代的な評論の重要性も再確認されると思います。
もう一つ、相互依存的な関係のため厳しい視点の評論が書きづらい、という件は、まさに。批判などネガティヴに捉えられることは、実際言いづらいですよね。ただドキュメンタリー映画がそうであるように、客観的なものなどそもそもあり得ないと思うんです。評論もそうだと思います。誰がいつ何をどの媒体で取り上げるかだけでもすでに中立ではありえない。それを批評的に念頭に置きながら評論を書くことが重要ではないでしょうか。と同時にそれを踏まえた上で、主観を交えながらより自由に評論を展開していく試みもあると思っています。自身への批評のないまま主観的な記述を展開したり、対象を攻撃したりすることは避けるべきだと思います。ただ批判するのではなくて、創造的な議論や評論の未来につながるような問題提起であれば意味があるのではと。批判でもそこに反省性があれば、それに呼応していくことやその批判の可能性を救い出して繋いでいくことが評論にはできると思うんです。それは炎上とは違うものですよね。簡単に炎上させない技術を途絶えさせないようにしたいですよね。
例えばですが、1995年以降にネットによるクリティシズムが可能になりました。e-flux journalなどは、それ自体で一つのアートの現場を形成しています。あるいはヒト・シュタイエルは、作品の制作とネット上での言論活動をとりわけ2010年頃から同時並行して展開していますよね。彼女の言論活動を見ていると、移動しながら書いている印象を受けるんです。変化しながら書いているというか。それはネットの存在があって可能になる論評のあり方だと思うんですね。そういった方向に批評や美術評論が変わっていくことについても考えたいですね。
AM 私もヒト・シュタイエルのテクストの愛読者ですし、授業で使ったりもするんです。彼女には哲学のバックボーンがありますよね。カジュアルな語り口でハードコアなことにアプローチしている。非常に特徴的な作家だと思います。ただ広い目で見ると、そのあり方はエリートな教育を受けない限り達成できないかもしれません。美術の世界でも二極分化や分断が進んでいるように思います。
四方 アンドリューさんも関わってくださっていますが、美評連の中で異なる世代や分野の会員間の対話を活性化させるプロジェクトを、国際関係・若手育成WGで構想中です。例えば、アンドリューさんから提案いただいた「メンター制度」のようにキャリアのある評論家と若手がコミュニケーションする仕組みを考えています。これは相互メンターだと思っていて、お互いが学び合えると思うんです。分断を起こさないためにはコミュニケーションや対話が重要です。
AM 私の経験ですが、雑誌などに寄稿した際に校正が戻ってきますよね。文法上の間違いもありますが、議論に踏み込んでくるような指摘があったりもします。それによって良い評論になっていくという実感があるんですよね。つまり評論というものはある種の相互作用があって完成するものだと思うんです。しかし、次の世代では、そういった良い編集者のいる雑誌を通さずに、単独で文章を発表することになっていくかもしれません。そのことを心配しています。
四方 そうですね。ネットクリティシズムが台頭した90年代半ばにおいては、投稿したものを多くの人が見てくれて、それを直してくれるようなコミュニケーションがありました。ある種のコラボレーションのような評論の作り方ですよね。特定の編集者に依存せずに、複数の人が関与する共同創造としての評論がありうると思います。これは、個人がその発言で炎上するような事態とは真逆のことだと思うんです。
「コラボレーション」を広く捉えるなら、例えばポスト人新世の時代というパースペクティブでは、人間だけでなく人間以外の様々な存在––動植物や石、微生物や水、空気、デジタルやバイオデータなど––も含めて地球上の、そして地球外からのものがアクターとして絡まり合い、相互依存しながら循環し、組織化や分散を続けている、そのようなダイナミックな情報の作用として世界を見ることができるのではないでしょうか。現代の科学・技術では生命と非生命、能動と受動などの境界を策定しにくい状況になっています。対立項として見るのではなく、一つの循環の中で往還する動的な現れと見なせるのではないでしょうか。「コラボレーション」という概念も、人との間に限らず様々なものとの関係において捉えることができるのではと。
マルチスピーシーズ人類学においては、E・コーンの『森は考える』(亜紀書房、原著:2014)など、人間以外のものからの視点が提起されています。近代的な眼差しから脱却するそのような世界の中で、あらためて人間とは、美術とは、美術評論とは、そして人間だけでなく世界におけるその可能性とは、と考えていく時代にあると思います。美術の起源はホモ・サピエンスもしくはそれ以前にあるとされていますが、それは同時に技術の発達と並行していました。ご存知のように、ギリシャ語の「テクネー」には芸術も含まれています。人間は自然の一部でありながら、自然を技術を通じて対象化する術を持つことになった。それに対して芸術は、自然への畏敬の念に根ざした存在への問いを発してきたと思います。
近代において、20世紀へと至る美術のシステムが形成され、それとともに美術評論も形成されました。現代では、このような近代を基盤としたシステムとそれが排除してきた様々な芸術や叡智を、デジタルを含めた情報技術を介して結びつけ共有していくことが求められていると思います。技術が人間の熟考を凌駕する勢いで進歩する中、美術からの問いかけがますます重要になっています。人間だけでなく、人間以外の存在も含めた世界のあり方を提起していく必要があるのです。美術も人間による人間のためのものだけでなく、人間以外の存在との時間や空間を超えた共同創造的なものと見なすことができると思います。そのような時代における美術評論の可能性にも向き合っていければと。
日本の美術は、非常に多様で長い歴史を持っています。明治以降の近代化によって否定してきたものの豊かさに向き合い、それらを生み出してきた多様な自然や精神風土––清濁が入り混じった––を掘り下げること。決して簡単なことではありません。しかしそのプロセスを経て、日本で美術や美術評論の新しい生態系が生まれるならば、グローバルな美術の未来に貢献することができるでしょう。
AM たまたま『森は考える』を読んだばかりで、翻訳家として携わってきた菅木志雄の著書と共通点が多く、驚きました。前者の著者であるコーンは森を本質的な「自然」としてみるのではなく、チャールズ・サンダース・パースを参照しながら人間と動物、植物、地理などをつなぐ記号過程として再解釈します。1960年代末から活躍している菅は「もの派」の中心人物の一人として知られていますが、当時益々盛り上がっていた消費社会・情報社会に対してある種の「ものの現象学」を提示するために、唯物論ではなく記号論をたくさん参照していて、実はコンセプチュアル・アートに近い仕事をしています。つまり、コーンと同様に、記号論を「不自然」なものとして拒否するのではなく、記号論の限界状況を探ることで脱人間中心主義の世界観を試みています。菅にそれがいち早くできたのは、西田幾多郎や古代インドの龍樹からパースやヤーコプ・フォン・ユクスキュル、ジル・ドゥルーズまで読める環境にいたからで、日本で多元的に世界の思想を吸収できた背景もあったからでしょう。
そこからもう一人の著者、エドゥアール・グリッサンを連想します。フランス領マルティニーク出身のグリッサンは「全世界が列島化し、クレオール化している」状況の中に土着性を帯びたグローバルなあり方、そして新たな創造の可能性を見出しました。面白いことにコーンもクリッサンも、植民地の現実を否定せずに、「内」と「外」、「先住民・有色人種」と「白人」のパワー関係が複雑なもつれ合いにあり、相互的に影響し合うものだと認めます。
海外発信には未だに非対称的な仕組みが残りつつも、それは来るべき日本現代美術評論のあり方にとって大きいな手がかりだと思います。まず、新しい価値観を生むには神話的な「西欧」(他者)に対して単一的な日本像を取り戻そうとするのではなく、日本のつねにすでにある複数性や複合性を認める必要があると思います。また、そのために日本帝国の歴史とその後遺症をしっかり見つめる必要があると思います。実際に今年(2022年)の釜山ビエンナーレでも見られたように、韓国、台湾、マレーシアなど、アジア諸国・地域の作家たちが旧日本帝国を取り上げる作品を作り、現代美術の現場で「日本」をめぐる議論はすでにトランスナショナルな次元に到達しています。
グリッサンが好んで使っていたセリフがあり、その初出が分からないが、最近ハンス=ウルリッヒ・オブリストが書いた文章に次の通り引用されています。「I can change through exchange with the other, without losing or diluting my sense of self.(自己の感覚を失ったり希薄にしたりすることなしに、私は他者とのやり取りexchangeを通して変わるchangeことができる。)」(Édouard Glissant, as quoted in Hans Ulrich Obrist, Artnet News, October 11, 2021, https://news.artnet.com/opinion/edouard-glissant-hans-ulrich-obrist-2003069)それは評論家の仕事をよく表す言葉だと思います。つまり、絶対的な客観性を持つことは不可能だとしても、評論家は、他者を受け入れながらも自分を超えた視点を探ろうとします。現在、メディアのあり方が劇的に変わり、知的な労働の価値が根本的に問われつつある中に、それができるような環境を維持することがより大事になるでしょう。
2022年10月16日 銀座にて