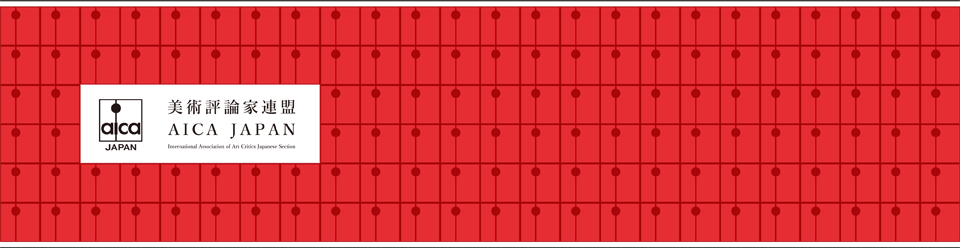林道郎(美術評論家連盟 会長)
先日の美術評論家連盟のシンポジウムは、大変聞き応えあるものだった。コロナ禍の中、オンライン配信という初めての形式での催しになり、従来の実地開催からのマイナス面もあるが、同時に、予想をはるかに超えた視聴数があり、今後に向けて、ハイブリッド形式の可能性も含め、いろいろと考えさせられる結果となった。会長として、参加くださったパネリストのみなさん、視聴して下さった方々にあらためてお礼申し上げたい。
内容については、第三者的な視点から黒瀬陽平さんがレビューを書いてくださる予定になっていることもあり、私はここでは踏み込まない。シンポジウムの議論に触発され考えたことをごく一部、抽象的な形でここに備忘録的に書き留めておくこととする。
*
シンポジウムの最後の感想で少し触れたが、近年「表現の自由」が容易に侵害されることが増えている要因の一つが、政治の世界における右派ポピュリズムと、それと深く結託する情動的ナショナリズムの台頭であることは間違いないだろう(左派ポピュリズムの可能性も現在政治思想分野では盛んに議論されていて、その動向と表現の自由の問題はここではおくとして)。それが、今回の新型コロナ危機の世界的席巻の過程で、ますます避けて通れぬ問題としてあらわになっている。もちろん、国家間だけではなく、階級、人種、ジェンダー、セクシュアリティなどをめぐる対立も鋭い断面をあらわにしたのであるが、そのような、一見、別の領域でのことに見える分断も、多くの場合、幻想としてのナショナルな文化との象徴的同一化に根差す、権威主義的な(背後に脆く崩れ去る不安を抱えた)主体の欲望によって媒介されていることが少なくない。
それに関連して、「多文化主義」という言葉をあらためて想起してみたい。個人的なエピソードで恐縮だが、私は、この言葉が使われ出した頃、その肯定的な含意と同時に、様々な文化集団が互いの差異を保持しながら領域確定を図るための、いわば不干渉のイデオロギーになってしまう危険があるのではないかという不安を感じた。もう何年も前になるが、その懸念を知り合いのカナダ人に話したら、不思議な顔をされた。それもそのはずで、そもそも「多文化主義」をもっとも早く標榜した国の一つであるカナダでは、この概念は、少なくともその理想において(現実の運用が問題含みであることはとりあえず脇に置き)、異なる価値観を持った複数の集団が、一つの国つまり同じ場所で共生していくために、相互に敬意を払いながら話し合いを可能にする政治空間を仮設し、さらに持続的に更新するための思想だったからだ。
その友人の怪訝な表情を思い出しながら、「多文化主義」のその原義を忘れぬようにといつも思うのだが、現実には、国家間や共同体間の関係において、やはり不干渉のイデオロギーとして機能してしまうことも多く、残念ながら、コロナ騒ぎをへて、その傾向はますます強まっているようにも見える(WHOをはじめ、数々の国際機関の弱体化はそのことの副作用と言える)。
多様性という概念も、同じ問題を抱えている。つまり、今やそれは、国と国、あるいは個人と個人など、様々なレベルで、必要な関係構築のためのコンタクトを阻み、「距離」を絶対視し、傍観者的な態度に安住する心性に口実を与え、不干渉(=不感症)のイデオロギーとして機能しつつあるのではないか。
むろん、干渉しあえばいいというものではないし、表現に携わるものが、個としての自立(孤立)と責任を、それが幻想と知りつつも起点としなければならないこともまた然りだ。しかし、そのような個もまた、対話的・相互差異的な関係性の中から持続変容的に「現れる」ものだということを認識できなければ、よってたつ土壌自体を、思弁的にも感性的にも、反省の対象にすることができなくなる。相互不干渉の安易な肯定は、言い換えれば、「自己」が所属する文化の自明性を疑わず、その幻想を成立させている他者との関係性自体を考察の対象にする「批評」的倫理を立ち枯れさせることになるだろう。
さて、こういった相互不干渉の論理の裏側では、多様性をめぐってもう一つの事態もまた進行している。つまり、多様性の言挙げが、その喧々諤々の交通を可能にする場——正しく「アゴラ」と呼ばれるべき場——の維持を促すのではなく、逆に、異質なものを排除した上で設営される最大公約数的な場——フラット化された擬似アゴラ——の称揚に向かうという傾向だ。いろんな人が観にくるから、その誰をも不快にしないような表現こそが多様性の尊重だというような考え方だ。
このような「多様性」の考え方と結託しやすいのが「公」という概念(日本では特に)であり、それは、あいちトリエンナーレ2019や空中分解したひろしまトリエンナーレをめぐる言説でますます明らかになった。「税金を使うのにふさわしくない」という脅迫的な言辞と相まって、このように狭量かつ空虚に抽象化された「公」概念は、しばしば「国民」の名によって偽装される価値規範にしたがって、その規範そのものを批判的に検討しうる外部的な思考を排除した、思考停止=自同律の場になってしまう。本来ならば、多様で、時にマイナーな「私」たち(あるいは普通の「私」にだっていつ訪れるかしれない突然の外部的な啓示)の声や身体や情動が、自由に(他者の権利侵害を伴わない限りで)提示され交わされる場こそが、「公」として守られるべきであり、そのことによって「公」概念自体が日々更新され、多元化されるべきであるというのに。
この、相互不干渉の論理と、空虚な最大公約数的な価値の反復という、矮小化された転用から「多様性」概念を取り返すためには、当然のことながら、様々な社会・歴史・文化・政治的な力線の交錯する結節点として「現れ」ている特異点としての「私」たちが、表現を介してそこに回帰し、摩擦やすれ違いなどをも発生させつつも、関係性を形成する場が持続的に保たれなければならない。「表現の自由」という理念の重要な役割のひとつは、そのような場の開設と維持を促し、種々の「声」を遅滞なく媒介することであり、その場を通して社会全体を自同律的な反復から解放し、複数の変容の(未決の歴史の)可能性へとひらくことに他ならない。
*
では、その可能性の開拓にとって「芸術」という営みはどんな意味を持つのだろうか。なにも「芸術」をことさら特権化する必要はないが(そこで起こることは日常生活における知覚や認識と通底していることを再確認しつつ)、ここで想起したいのは、近代以降に独特の変容を続けてきた「芸術」の歴史が、民主主義という社会政治体制の発達そして、既成の共同体を超えた交通の可能性の拡張と深く関わってきたという事実だ。民主的な社会を展望させ、発展させるための想像力の「現れ」にとって、芸術の世界が押し広げてきた、自己反省的な意識/感性の展開と、その多元的な分岐の過程は、常に、ある「例示」であり続けてきた。
ここでいうのはしかし、単なるイラストとしての「例示」のことではない。指示機能に還元されるだけでは済まない、それ自体が過剰な感覚的現前としても存在する「例示」のことだ。別の言い方をすれば、その具体性から、これまでにない価値(を可能にする表象システム)の体系が生成するかもしれない予兆を孕んだ生産物として存在してきたということだ。近代以降の芸術の歴史が、「反芸術」や「非芸術」的な生産物を契機にして「芸術」をめぐる別の記述体系を次々と編成してきた歴史でもあるのは今さら確認するまでもない。
この断層を内部に抱えた存在=例示は、それを受けとる私たちの側にも、なにかしらそのような内的な断層を引き起こさざるをえない。芸術作品の経験が、つねに「予感」というモードに付き纏われるのはそのためだとも言える。つまり、その還元不可能な単独性は、既成の表象システムの中に位置付けることができないという意味で測定を許さぬが、にもかかわらず、なぜか何か大事なことが起こっているという感覚を持たせる。この時間的な分裂の経験こそが、芸術の経験であり、ラディカルな意味での(私たち自身もその中で変容を余儀なくされるような)民主主義的な空間への通路であり、そのような意味での「例示」なのにほかならない。このような経験の中で個人は、現にある人間社会の中で機能主義・関係主義的に規定されたアイデンティティに対して過剰である「例示」としての(来るべき)自己の本源的な存在=自由の過剰性を「予感」することがあり得るだろう(「自由」という空虚なシニフィアンにある感覚可能な具体性を与える活動としての芸術)。
さらに、この「予感」が指し示す可能性は、二つの根源的な問いを喚起する。一つは、この過剰性が「社会」という概念そのものの再考を迫るということだ。先日のシンポジウムでも話題になっていたが、接続の可能性は、人間という領域を超えて、動物や事物、そして技術にもまた媒介された「社会」を想像することを可能にし、そのような視点から「人間」(とその暴力)を問い直すということもまた可能になる。もう一方で、重要なのは、この「予感」が決まった方向を持たない、必ずしも直線的な時間を前提にするものではないということだ。芸術経験の時間が垂直の時間を立ち上げるといった言い方がなされることが多いのはこのためだが、垂直という限定もまた正しくはない。その予感は、複数の無政府的で非連続的な飛躍に向かってひらかれているというべきなのだ。
したがって、なにがしか「人間」を自明の前提とし「客観的進行」を装う社会システムに対して、その進行の見かけの自然性を脱構築し、新しい社会あるいは共同体の創設の可能性を示唆し(さらにそれさえも絶えず解体させ)ていくのが、根底的な意味での「政治」であるとするならば、芸術とは、あるいは美学とは、優れて政治的な例示の営みであると言ってもいい。「多様性」という概念は(その限界の露呈も含め)、そのような意味での芸術の営みとふかく関わる概念であるはずだし、単に現状における相互不干渉的な価値の併存を意味するのではなく、むしろ「現在」という時間を相対化する複数の時間の駆動の可能性を見据えたものとして取り返されなければならないのだろう。
コロナ禍の中で息苦しいまでに私たちの生活意識を支配してしまっている現在という時間への過剰な同期についてはすでに多くの指摘があるが(先日のシンポジウムで議論されたプロジェクトやイベントもまた、そのような過剰な同期性を相対化することを特徴としていた)、芸術表現が可能にする異時の非連続的な同期の経験、あるいは、既成の人間や社会への安住を相対化するラディカルな多様性を「例示」する力、それはやはり、侮れないし、むしろますます貴重になりつつあると、言わざるを得ない。