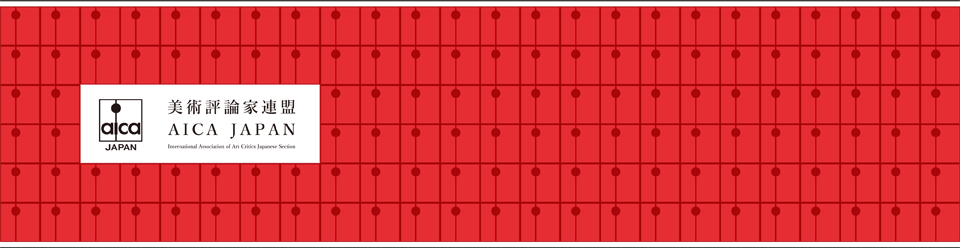塚田優(視覚文化評論家)
2018年11月11日、美術評論家連盟の主催するシンポジウム「事物の権利、作品の生」が東京藝術大学にて開催された。告知フライヤーには、今春発覚した東京大学による宇佐見圭司の絵画《きずな》の廃棄を受けての企画であることが謳われている。しかし本シンポジウムでは、そうした当座の状況にとどまらない広範な議論が展開された。作品に生があるとすればいかなる状況や観点がありうるのか。そこから敷衍されうるであろう事物の権利とはなにか。警鐘をならすべき現代の時代精神、理論の変遷、翻弄される作品、美術館の拡張傾向、近年の思想的潮流など様々なトピックが紹介された当日の模様を以下でレポートする。
〈前半|発表〉
まずはじめに実行委員長を務めた沢山遼による趣旨説明もかねた発表が行なわれた。沢山は作品の喪失について、その出来事は作者と作品それ自体に直接的な被害を与えることになるが、そこに孕まれていた様々な知的体系と解釈の可能性も同時に抑圧する事態にもなりかねないことを主張する。また、こうした状況は廃棄というケース以外では検閲によって発生することも指摘し、一昨年の連盟のシンポジウム「美術と表現の自由」とも今回のテーマが通底していることに触れながら、そのときにはスポットをあてることが難しかった作品それ自体について今回のシンポジウムでは議論していきたいという企図が語られた。
沢山は東大による作品廃棄をきっかけとして表面化した社会の無自覚について、阿部良雄による宇佐見についてのエッセイ「代名動詞の絵画」を取り上げながら、彼の絵画に見出すことのできるような、制作者という主体と、事物としての作品の透明な関係を解体する自律的な振る舞いに、作品の(ある種中動態的な)生が見出せるのではないかという。そこから続けて、取り壊しの可能性が浮上し、連盟が意見書を中野区に提出した後藤慶二による設計の旧中野刑務所正門を取り上げる。長谷川堯『神殿か獄舎か』にある指摘を踏まえながら、それを大正期における自我の目覚めの反映として位置づけ、その建築の内部の充実は、「自己の拡充」として目指されたものだと述べる。
こうした人間の生と関係を取り持とうとする作品の在り方について、沢山は事物に意識を内在させる村山知義や、岸田劉生のベルクソン的な「生の哲学」とも近似する方法論的共鳴などにもコメントし、柳宗悦の先導した民芸運動における唯物論的ヴィジョンへと接続する。一般的な理解では自我の芽生えとして回収されがちな大正期の文化を、主体の脱構築として再定義し、発表は締めくくられた。
池野絢子の発表は理論的な軸を据えたものとなった。池野はまず廃材や、布などの日常的な素材へのアプローチを特徴とする1960~70年代のイタリアの芸術運動アルテ・ポーヴェラの代表的作家であるミケランジェロ・ピストレット《ぼろきれのヴィーナス》の60年代と80年代における展示の違いを例に、脱物質化以後の芸術に見られるコンセプトの重視から引き起こされる作品の歴史的価値と美的価値の関係に着目する。
作品に内在する歴史性と、そこに表象される美的な側面を考えるにあたって池野は、アロイス・リーグルの『現代の記念物崇拝ーその特質と起源』とチェーザレ・ブランディ『修復の理論』を比較することを提案する。この2冊の出版された時代背景はもちろん異なるものの、何を作品において価値のあるものとして見なすのかという論点においては、今でも示唆に富むものだ。
リーグルの著作は後代による発見、つまり経年価値への注目によってその議論が成立していることをまず池野は指摘する。それによってあらゆるものはモニュメントたりうることになり、芸術的なるものと歴史的なるものの分別が原理的には不可能になるのだ。すべてを歴史記念物として優劣をつけないスタンスは彼の様式論に端を発するものであるが、それはルネサンス的価値判断とは異なる、記念物崇拝の性格に再定義を促すだろう。この前提からリーグルは記念物の価値を記憶の価値と現在的な価値に大別し、現代日本の事物に対する関心低下は、記憶の価値の忘却として認識されるべきものであると指摘する。
リーグルのいう記憶の価値は経年も含んだ、大衆でも容易に感知できる特徴であり、さらにそれは、事物の生を認める発想とも結びついていたという事実は、本シンポジウムのテーマとも強く共鳴する観点だった。
次に紹介されたのはチェーザレ・ブランディ『修復の理論』だ。リーグルとの比較においてふたつの重要なポイントを池野は取り上げる。一つは芸術作品の美的な価値の主張であり、もう一つは作品に流れる3つの時間についての認識だ。
ブランディは歴史的要件よりもときに美的要件を上位に位置づけ、修復もまたそれにのっとってなされるべきだと主張する。ここにはリーグルとは強調点を異にするものの、互いが補いあうような関係性が見出せるだろう。リーグルは時間を歴史性と現在性に二分する理路から自身の理論を構築したが、ブランディはこれに対し時間を3つに分けた。一つは作者が制作する時間、二つめは制作の終わりから観者の前に現れるまでの時間、三つめが意識において芸術作品がひらめく瞬間である。とりわけ第二の作品が観者の前に現れるまでの時間を重視する姿勢は、その経年への着目においてリーグルとも似通っている。
池野の発表はこうしたリーグルとブランディの理論を通じて、美術館に収蔵され、未来の観客の視線に晒されることになる作品の「読み替え」についての問いを投げかけたといえるだろう。
金井直の発表もまた美術史に裏付けられた、さながら感性の考古学といった様相を呈するものだった。
生というシンポジウムのテーマをなぞり、金井は古典的芸術としての彫刻に引導を渡したヘーゲルや、彫刻の停滞をある種の退屈としたボードレールを引き合いにしながら、彫刻の死という話題を最初に取り上げる。そして早々と叫ばれたその「死」の一方で、彫刻の「生」は、モデリングの問題と関連して浮上したという史実の紹介が続く。リルケが語った生動する面についての考察に代表されるこれらは、近代的な彫刻観を形成し、それらの言説のなかで語られる彫刻=モニュメントの不調は、台座からの離脱を述べたロザリンド・クラウス「展開された場における彫刻」にも影を落とす今日的な問題であると指摘する。
モニュメントの地位低下、そして表面の問題はどのように考えるべきなのか。金井はこのような議論のフレームを設定し、新古典主義時代の作家アントニオ・カノーヴァを梃子に考察は展開された。カノーヴァの彫刻によって喚起される記憶を、台座の強調と関連付けながらも、金井はそこから表面の処理へと話題を転換する。大理石表面の照りを抑える最後の仕上げへの配慮によって引き起こされる鑑賞における多様な経験は、アレックス・ポッツも指摘するように、ミニマルアートとも共通する間主観性を作動させるという。こうした表面をカノーヴァ自身が「ヴェーラ・カルネ(真の肉)」として位置づけていることに着目し、それはジョージ・クブラーが『時のかたち』のなかで位置づけるような「自己シグナル」として捉えられるのではないかと述べた。
しかし、このような美学は19世紀に入りより自律的な美学へと変化することになると金井は続ける。無垢な表面を求める北ヨーロッパ的な趣味の台頭によって、官能的な大理石よりも不活性な石膏が賞揚される時代がやってきたのだ。純白への傾斜は、人種という政治的な論点を孕んでいることにも注意を促しながら、こうした強力な白紙還元があったからこそロダンの表面の操作が際だったことに触れ、だが一方でこうしたモダニズムの観点が確立されたことにより、カノーヴァの作品は過剰な洗浄修復が施されたことを指摘した。表面の差異が圧縮された平板なフォーマリズムは、結果的に作品の質感を変質させる事態を引き起こしてしまったのだ。
これらの事例は安直なヴァンダリズムとは異なるものの、美学的言説が場合によっては彫刻の生を損なうことにも直結するという、デリケートな問題を私たちに突きつけている。
蔵屋美香は、美術館の現場で事物や作品の生、保存がどのように考えられているのかを中心に議論を展開した。そこで浮かび上がるのは美術館の「生」である。欠けている傾向の作品を収集しながら、コレクション全体は拡大し続けており、それらは美術館運営のための経済資源として貸し出され、流通する。作品はグローバルなアートワールドのパワーゲームの重要なアクターとして振る舞っているのだ。こうしたオブジェベースの施設としての美術館の在り方を紹介すると同時に、60~70年代の非物質化された芸術をどう美術館が収蔵するかが90年代以降問題となっていることも提起された。そしてそれは、美術館のブランチ開設の試みと並行して進行した事態であったという。とどまることのない拡大へと突き動かされるミュージアムは、その物理的な限界を超えようと建て増しをし、メガ・ミュージアムへの道を歩んでいる。
蔵屋はそうした欲望をアンドレ・マルローの「空想美術館」に関連付けた。「museum without walls」と英訳されるその概念は、壁の不在を担保に成立するコレクションの無限の拡大を理念的に正当化するだろう。しかし一方で、マルローの構想にはオブジェたる作品を非物質化したうえでの収蔵も視野に入っており、その点については、現場ではまだまだ慎重に議論している最中であると述べた。
こうした現状と収蔵庫の物理的な限界を鑑みた上で蔵屋は、収蔵の基準や、美術館の人間の生を超えたスケールにどう向き合っていくのかが今後の課題であることを述べ発表を終えた。
星野太は、本シンポジウムへの疑問を真っ先に提起し、これまでの発表者との差別化を図りつつも、より根本的な問題を志向する。
星野はシンポジウムのタイトルである「事物」と「作品」が、果たして同じ俎上に載せられるものなのかという問いを発する。事物の権利を考えるならば、作品などのカテゴリー分けは設けるべきではなく、全事物に等しくそれは認めなければならないはずだからだ。そしてそれに続けて「生」に対してもその性格が批判的に検討されていく。
まず問題視されるのは作品を生物学的な観点から語るときの誤謬だ。たとえばスタンリー・カヴェルは、ロザリンド・クラウスに人類との類比によって芸術作品を論じていると批判される。ここで取り逃されているのは作品の非有機的な次元に他ならない。例えば、ボリス・グロイスの生命観はドイツ観念論やフランクフルト学派に立脚したものであり、生命をかならずしも伴わない存在的なエレメントもまた生命に含まれていることを指摘する。とするならば我々の生をめぐる了解には亀裂が入り、絵画の筆触までもがそれ単体として浮上するだろう。こうした観点は物質の生を異なるものの共存として捉え返し、複数の秩序の認識を可能にするはずだと星野は述べた。
生への透徹した眼差しはさきに検討された生命の有機性をも再審に付す。高アルカリなど極限の環境のみに生息が可能な微生物は、私たちが想像するような生の定義を根本から覆し、生の輪郭を曖昧にさせるだろう。思弁的実在論をはじめとした昨今の哲学的議論はこうした知見を援用しながら思想的展開を図ろうとしており、作品の生を考えるにあたっては、このような点に無自覚でいることはできないのではないかと警鐘をならす。
〈後半|パネルディスカッション〉
作品と事物の権利、そして生をめぐって多様な問いが提出された前半を終え、後半は発表者に林道郎をモデレーターに加えてのパネルディスカッションが展開された。
まず人間中心主義に対する警戒において一貫していた星野の話題と沢山の事物に対する眼差しに共通項を見出した林の見解に付け加えるように、沢山は念を押す。作品は著作権といった人物に帰属するものとは異なるものだと述べ、そこに込められた知的体系のユニークさを引き出し、昨今低下していく作品へのリスペクトを継承するのが批評の役割であると語る。ビックデータやブロックチェーンなどを活用して作品を一元的に情報に還元し、管理することに対する注目が集まっているなかで、こうした姿勢を言説生産者が打ち出すことには一定の意義が見出せるだろう。沢山は合わせて今年5月に報道された政府による「リーディング・ミュージアム(先進美術館)」構想もまた同根の問題であると指摘し、倫理的な態度を表明した。
時勢が時代によって変わっていくことも重要な論点であることを林はコメントし、そのような観点を孕んだ発表を行なった池野に補足や全体を通しての所感を求めたところ、リーグルとブランディの比較は、全てを平等な記念物として捉えるリーグルを対比することで、作品の自律性を信じるブランディを際立たせる意図があったと説明する。作品の生について、例えば色褪せた宗教画への加筆などは文化財に対する破壊行為であったとしても、宗教的な文脈では作品の生を回復するための行為として正当性を持つこともあると述べ、慎重な議論を呼びかけた。
林も整理するように、今回のシンポジウムは作品に対してたったひとつの線的な生を想定すべきではないという主張は各論者に一貫していた。金井が彫刻の修復の問題に絡めて述べたように、作品の魂はひとつではなく、その都度「継起するオリジナル」として我々に知覚されるものなのだ。
そんな作品の生は、実際の美術館運営にどのような影響を及ぼしているのか。林の問いに対して蔵屋は、作品を取り扱うのはあくまでも学芸員=人間であり、その限界において対処するしかないと応答する。およそ13000点を収蔵している国立近代美術館では、作品を取り扱うことのできる資格保有者12人で収蔵作品の管理をしている。一人あたり1000点以上の作品を担当することの労力負担と、そこに昨今のミュージアムの拡張傾向も加えるならば、人間のスケールを超えた思考が現代の美術館には求められてきているのではないかと述べる。
林はテート・ギャラリーが郊外に保有する収蔵庫についてもふれ、日本の収蔵庫事情について蔵屋に質問を投げかけたが、スペースの拡充になかなか至らない厳しい台所事情も吐露された。しかし、だからこそコレクションの基準を明確にしているという。アメリカでは日本のもの派をはじめ再制作された作品も数多く収集されているが、国立近代美術館では基本的に再制作は対象にならず、複製がないことや、作者による再制作だと判明しているもののみが収蔵されている。こうした厳しい基準が設けられているにも関わらず、アーティストの収蔵への欲望は高まってきており、反権力を標榜した60年代的価値観ではなく、どのように美術館と恊働するのかという意識変化が育ってきていることも蔵屋は付け加えた。金井の指摘によると、アルテ・ポーヴェラもまた1970年前後に収集可能なものに作品が変化し、その傾向は80年代後半にさらに強まったという。作家にとって美術館とは、作品の生を保証する、重要な存在であることが改めて確認された。
しかしそうした美術館における作品の生は、一概にそのまま首肯できるものではないだろう。60年代美術の再構築展が開催されている現状に池野は警戒感を示す。当時の追体験というノスタルジックな装置では、オリジナルとかけ離れてしまう危険性と隣り合わせだからだ。
星野が発表した存在論的な問いに関しても、ディスカッションではより深い議論がなされた。林は「be」という形容のほうが「life」つまり「生」という人間中心主義から脱却できるのではないかと述べ、人間的なメタファーの有効性を改めて問いかける。
星野はそれに対してあらゆる存在を「be」としてフラットにしてしまうことは価値の問題をオミットしてしまうことに触れ、それが政治的にしか主張できないことを踏まえながら、やはりそれは「life」の問題として取り扱うことでその特異性が認知できるのではないかという見解を示し、オブジェクト指向存在論などの現代哲学への距離感を表明する。エコロジカルなイデオロギー性を持つことが却って美術においては非政治性に解消されてしまうという林のコメントが示唆するように、こうした最新の理論の援用には慎重でなければならないだろう。ただ沢山も指摘するように、芸術作品それ自体は非人間的なものであるということもまた揺るがしがたい事実だ。作品は人間的なものとそうでないものをネゴシエーションする可能性を秘めている。しかしだからこそ、芸術作品が特異な、非人間的な例外的な生であると主張することの政治性に、私たちは鈍感ではいられないはずだ。
そんな作品と私たち人間が結ぶ関係について、ふたたび宇佐見圭司の《きずな》へと議論は舞い戻る。林は9月に東大安田講堂で開催された宇佐見をめぐるシンポジウムにおいて高階秀爾も紹介した黒井千次「拒絶のキャンバス」を引用しながら、自らも知らぬ間に関係してしまうこともまた作品のひとつのあり方なのではないかと投げかける。その無意識は意識へと転換することで、雄弁に語りかけてくるものだ。沢山は《きずな》に内包されたワッツ暴動という文脈を取り上げつつも、作品にはスピノザがいうような他から付与されたものではない、内在的な権利としての自然権があるのではないかと洞察する。
無関心のなかで破棄されてしまった《きずな》は、ブリュノ・ラトゥールが『近代の〈物神事実〉崇拝についてーならびに「聖像衝突」』において分類した、破壊しているという自覚のない「無邪気な破壊者」によってなされたものだったことに沢山は触れ、古典的なヴァンダルとは異なる様々な破壊に事物がさらされることへの警戒感を強めた。こうした人間的な憐憫すら介在しない破壊は、美術の関係者それぞれが抗していかなければならない喫緊の問題だ。
会場からの質疑応答では、《きずな》をめぐって廃棄の証拠すらない現状に対する毅然とした態度を求める声も上がった。個別の事例に対する実質的な報告、決着が待たれるのはもちろんである。しかし沢山も述べるように、それよりもまず美術評論家をはじめとした言説の生産者が作品、ないしは事物に対して関心を持続し、そこから発せられる「シグナル」を感受し、社会へと発信し続けることが重要なのだろう。このような倫理を最後に共有し、シンポジウムは締めくくられた。