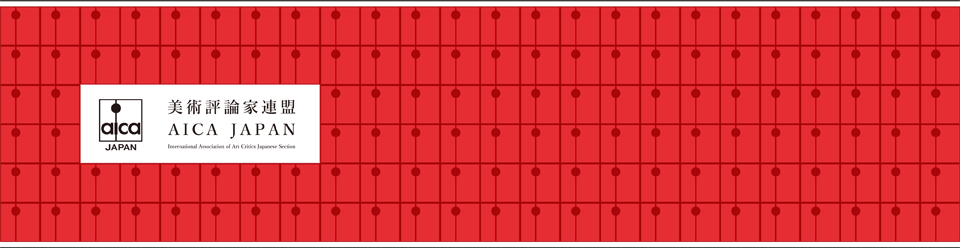『あいだ』の四半世紀
1990年代後半 鋭利であり続けること
光田由里
月刊『あいだ』の最新号は、2020年10月現在、255号である。
中性紙二つ折りの30ページほどのB5版、スミ1色、書店扱いはなく、年間購読または号数指定の事務局への申し込み、郵便振替で入手できる。『あいだ』の会発行、編集は福住治夫。紙面設計は穐葉さり、制作管理は新倉美佳と藤江民。印刷は石橋大、製本と郵送担当の「このあいだ社中」は、月1回の会合を続ける有志グループである。本誌に関わる人は全て無報酬で、長年変わらないメンバーで発行されているが、決して同人誌ではない。書き手は幅広く、年齢、職業、国籍も様々で、何度も登場する執筆者もあれば、1度きりの方も少なくはない。基本的に文字数制限はなく、長文は連載になる。広告は一度もなく、執筆者以外には寄贈もしない。号数が3桁になる前に、東京都現代美術館美術図書室が年間購読を始めた(所蔵は誌名が『あいだ』となった初号の32号から)と記憶する。ほかにも所蔵美術館はある。後期資本社会における、孤高の非営利・独立美術雑誌である。
今年になって同誌は「近々終刊いたします」と宣言した。年間購読は申し込めなくなった。が、「あいだの会」HPに全号の目次が公開されていて、遡ってバックナンバーを購入できる。同会HPの冒頭に「月刊『あいだ』とは」と、自己紹介記事がある。それをご一読いただくとして、経緯を簡単に記すと次のようである。
誌名は、「美術と美術館のあいだを考える会」に由来する。同会は、富山県立近代美術館(当時)で1986年に始まった大浦信行の版画連作《遠近を抱えて》(1982-85年)の展示・公開・収蔵をめぐる議論と措置をめぐって、美術関係者がこの問題を共有し、解決を考えるための場を作ろうと1994年1月にスタートした小グループだった。その会合のなかに、福住と藤江がいて、筆者は末席に加わった。すでに「大浦作品を鑑賞する市民の会」をはじめいくつかのグループが、署名活動や抗議行動を活発に行い、同じ94年に有志によって住民訴訟が提訴され、作家とその支援者は国家賠償訴訟を起こすことになった。これを受けて、改めて美術と美術館の現場の問題としてとらえ直すための発足だった。
会の活動を記す『事務局ニュース』が創刊され(1994年11月)、その増刊号に類する『あいだEXTRA』 の刊行も始まる。富山市の桂書房から、カラー表紙の立派な『あいだ』1号(1995年)、2号(1996年)も出版された。同会がこうした出版物を持ちえたのは、熟練の編集者・福住が、自発的のように見えていたのだが、編集を一手に引き受けたからだった。というよりも、福住が直接間接にこの問題と通じる、美術と美術館の大小様々な事件を見逃さず、関係者の文章を募りながら情報発信をし、活動の跡付けを残していった力業があったことに、同会の継続は大きく支えられていたと思う。
国家賠償請求が最高裁で棄却され、この会の凍結が決まる。メンバーが手をつないで輪になったことを記憶している。そして『あいだ』は存続することになった。
軽い体裁と軽くはない経緯をもつこの雑誌は、独自性が明確な、依頼原稿で成り立つ美術専門誌である。まず経緯からしても、美術館の社会性、とくに検閲問題に敏感に反応してきた。日本の美術館には、性と政治両面からの検閲は絶えず、バブル崩壊後の予算削減、地方自治体・行政のさまざまな介入、指定管理者制度導入、地域国際展との連携などいくつもの変転もあった。2014年光州ビエンナーレの検閲問題の際に、唯一の特別先行版と本誌(218号)を同問題と「表現の不自由展」の特集号とした。昨年の「あいちトリエンナーレ問題」では、馬定延、小倉利丸両氏の鋭利で詳細な原稿を2号(251.243号)にわたって掲載した。本誌はいわば富山から愛知までカバーしたことになる。
最も誌面が割かれているのは、日本の前衛美術研究である。戦中、戦後の前衛美術の、証言、資料紹介、研究をベースに、同時代動向に批判の目を注ぐのが、『あいだ』のスタンスだと思う。
「戦時下日本の美術家たち」の飯野正仁の連載は61回を数えた(210号、2014年)。続く1960年代から70年代末まで美術に関しては、高齢になられた作家自身のエッセイや作家インタビューが豊富で、生々しい証言が読めるのは、同誌の特徴だろう。同時代を知る関係者、批評家の文章も、大所高所からではなく、自身の体験として率直に語られてリアリティは濃く、ほかでは読めない親密さがある。これを可能にするのは、執筆者にも近しいコミューン的読者層なのか、編集力なのか。一方で最新の研究にも目配りがされ、若手研究者のエッセイや論文も潤沢だ。
美術館の各種講演の採録もしばしば行われ、他誌では見かけない美術館とのコラボレーションが実現しているのも、意外といえば意外である。独自企画の対談もあり、作家の未刊行一次資料の採録もある。国外ではとくに韓国美術の記事が豊富で、日本前衛美術との比較対象になっている。
追悼文に手厚い。作家論と言うにふさわしい充実の追悼文が多い。近年で突出しているのは、2006年に亡くなった松澤宥の追悼だろう、70年代初頭にヨーロッパで活動した松澤の国際性、諏訪における土着性、美学校における授業、コミューン的グループ活動など多方面にわたる証言や論考が断続的に続いたのは、単行本化するに値する。
回顧の記事だけではない。ジェンダー問題が地域を問わずひんぱんに取り上げられていることに触れておきたい。同誌のアクティヴィズムへの注目は、アイ・ウエイウエイに対する手厚さにもつながっている。海外展も含め、展覧会評も斬新なものが多いが、長文の書評に読みごたえがある。希少な自費出版、国内外の話題本は「編集部の書棚から」欄でも、踏み込んだ紹介がある。
連載の充実もある。たとえば宮田有香「内科だった、画廊だった―ふたたび」(59-95号)、西村智弘「日本実験映像史」全33回(87号-123号)、坂上しのぶ「James Lee Bayers "Days in Kyoto"」全10回(197号~209号)は、それぞれ執筆者の代表作のひとつになるだろう力作である。さらに同誌の屋台骨を支える並走者、稲賀繁美の「あいだのすみっこ不定期漫遊連載」は、140回を数える。日本美術研究の重鎮である同氏が、世界各地のシンポジウム、学会、展覧会に赴いてのレポートを柱に、時代も領域も自在に横断して最新研究動向の一端を伝えてくれる。「すみっこ」どころでないこの連載は、批評的な斜めの視線が実はまっすぐな世直し思想を基底にしている同誌の姿勢と、響きあっているのではないか。
などと、『あいだ』をなんとか粗描しようとしたが、やはり無理だった。筆者力不足のため、同誌については、福住治夫編集長その人そのものだと今は書いてしまうほかはない。
高島平吾の筆名で翻訳したトム・ウルフ著『現代美術コテンパン』(1984年、晶文社)がヒットし、ジャーナリスティックな慧眼による選書と読みやすい訳文により、翻訳者としての活躍が期待されていた福住氏が、なぜか大手出版社に背を向けて、簡易印刷ニューズレターから『あいだ』を生み出し、身をもって非営利月刊誌に育てて250号を超えた。氏がそこに投じたエネルギーの膨大さの前で、美術評論家連盟編集委員からいただいた「批評の場」という言葉をどうしたら使えるのだろうと、筆者は七転八倒して結果は出せなかった。
これは、伝説の1970年代白背表紙『美術手帖』を分厚く増頁し、赤瀬川原平の連載を守ってフリーになった編集者の仕事である。70年代からの業界仲間の方々が製作を支え続けているのも、見事というしかない。
生きて動いている美術は、美術館にそのままの形では収められない。収蔵庫からはみ出すから置いていくしかない重要な部分を、別の場所で活かし続けてくれるのは、作家とその関係者たちである。「美術と美術館のあいだ」はそこにあり、『あいだ』の位置もまた、そこにあるのではないだろうか。これらの文字は残り、これから研究対象になる。
準備されているだろう終刊号の企画が気になる。編集長のインタビューをぜひ掲載していただきたいと願う。せめてHP上なら文字数制限の心配はないのだから、いかがだろうか。