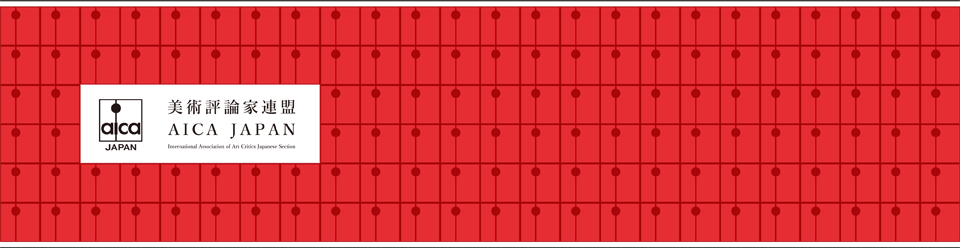『LR』と『LR Returns』
90年代後半から2000年代 批評のプラットフォーム
早見堯
『LR』は山本育夫の編集による美術雑誌である。名称『LR』は「Live and Review」の略号。Right and Leftが交錯しながら重なるニュアンスも含まれている。「隔月刊、マガジン、アート」として書肆・博物誌より1997年4月から2001年3月の24号まで刊行された。議論をライブで拡散するプラットフォーム的な雑誌がめざされていた。その後、よりライブ(なま) な「意見を交換し、議論しながらつくっていく情報でないと、意味がない。そういうところへ行くための過渡期」としてウェブマガジンが1号だけ試みられる。再び、紙媒体の雑誌『LR Returns』として復刊され、00号と2004年9月の1号から2008年9月の16号まで17冊だされた。
最初にことわっておきたい。わたしは当時、あまり読んでいない。興味がなかったからではない。個人的な理由で、こうした議論の場から距離をおいていたからだ。結局、『LR』は全24号のうち13号分、『LR Returns』は全17号のうち10号分しか読むことができなかった。ウェブマガジンはいまもネットで読むことができる。しっかり読んでいる読者や議論をかわした論者が多数いるなかで、こんな状態のわたしが書くことにすくなからず躊躇した。山本育夫から執筆の指名をいただいたのだが、一度、中村功と根岸芳郎との座談会にでたことがあるとはいえ、もしかしたら、ここに登場する論者とは、わたしの志向や立ち位置がちがっているから選ばれたのかもしれないと思い直した。それに加え、読んでとてもおもしろかったので、不適格を承知で書いてみることにした。
まず編集長の山本育夫の問題意識の根幹を確認することから始めたい。それはEditor’s Noteや連載「つづれ織り」に記されている。現在のこの国の美術の、本当の意味でのサバイバルのために役立つ雑誌でありたい。多くの美術館や画廊や作家、批評家、美術教師たちが激しい「リストラ」の嵐に襲われている、つまりはこの国の美術そのものが「リストラ」されているのだ。いったい「リストラ」している主体はだれなのだろうか?さらに、日本の美術の「閉じられた円環」の内部で、常に開かれているはずの外部を輸入してきたメディアによって、円環の内部で歴史が組み立てられていく。社会状況や言説空間がこうした危機に陥っている。われわれの美術界隈も「お花畑」から「リアルな場」へと転換しなければならない。だから、美術評論や美術表現、美術ジャーナリズム、美術館などのあり方を問う。ザックリまとめた問題意識と問題解決の方向である。
ここから、国立の美術館・博物館などの「独立行政法人」への移行問題、日本の美術での価値判断や権力の動き、ジェンダー、ソーシャリーな美術、日本現代美術の歴史の見直しなどがテーマとして登場してくる。同時に重要なのは、展覧会レビューや作家へのインタビューで、美術現場が臨場的に公開されていることだ。議論の契機として講演会や研究会、展覧会シンポジウムなどの再録などもある。それらを通して問題の核心を掘りおこし、書きたいから書いている論者が集まった、取り替え不可能なこの雑誌でしかできない論争が展開されている。
わたしは、1960年代半ばに銀座でクリスタル画廊を運営していた作家の坂本正治から、美術をやるのなら、『美術手帖』に載るか作品を売るか自己満足かはっきり決めてから始めよとさとされて、「閉じられた円環」の内部にもぐりこんだ。「日本・現代・美術」的観点からは空白の時代に青春と壮年時代を過ごしたことになる。いわば、「失われた美術世代」らしい。トホホ状態で身につまされながら読まないわけにはいかない記事もあった。とはいいながら、「閉じられた円環」だからこそ外部が輸入されてきたのではと、とりあえず抗弁しておく。
いくつかの議論で気づいたことを少しだけ記しておこう。「ジェンダーと美術」や「インド現代美術展」、「光州ビエンナーレ」をめぐる応酬だ。作家の「個の自発性」や作品の「質」、「作品が真に個の表現に達する」ことと、ジェンダーや土地・住民の固有性や戦争の歴史認識などを切り離して論じることはできないと思う。誰にも文句がいえない場所にあえて挑戦するみたいな意気ごみで始まったジェンダー問題への異議申し立てでは、どこかの宰相もどきに、観念派対肉体派、すなわちデスクワーク対フィールドワークに論点をすりかえては議論が展開できない。エッ!どうしてそんなに?と思う上田高弘の激怒がわかるような。これは、この誌上のほかでも論じられている作品の価値判断やだれが価値を決めるのかという問いにつながっている。同時に、作品の「質」だけを問うのは、ミディアムにかかわるモダニズムと、趣味判断にかかわるフォーマリズムの価値判断だと切って捨てられるのも寂しいものがある。この雑誌全体を通じて論じられたいくつかの議論の基本的な立ち位置のあり方は、「表現の不自由展」問題でもくりかえされつづけてはいないだろうか。
大西若人「本当に大切なのは「アート」と名付けられることではない」や、シンポジウム「おまえの何が現代美術(アート)なのか」の再録を、先の価値判断につなげて読んだ。このころから「美術(芸術)」が日常化した「アート」へとかわっていったのだろうか。「芸術の日常性への下降」は60年代半ばのメインテーマだった。さらに、ふと、『美術手帖』1970年7月号特集「これがなぜ芸術か−第10回東京ビエンナーレを機に」を想いだした。「美術(芸術)」を焦点にした円環から「美術(芸術)」と「アート」を焦点にした楕円に変貌したのだろうか。ここで、花田清輝&池田龍雄の「楕円幻想」を連想すると一挙に「1955年体制」にさかのぼっていく。彦坂尚嘉の「55年体制」論は、『LR』から派生した山本育夫編集の雑誌『ART STUDIES』で展開されそうになったが1号で終わっている。大西の「批評も含めた何らかの思いが生まれるような「物件」が「作品」なのかな、などとも思えたのだ」が妙に心に響くことが、なぜか虚しい。
笹木繁男「戦争画資料拾遺」は貴重なものだ。山本育夫の「ものえ派」はわたしの「平面体」と似ていて個人的に興味がある。深く展開されないまま終わって残念だ。だれかが指摘したように私記か私小説かというようなものもあった。わたしは清水誠一の私記だか私小説だかは興味深かった。
読める限りの雑誌を通読して感じたもっとも大きなことは、編集という仕事の力(使われ過ぎて力を失いつつある「力」だが)である。編集は、美術の文脈では描写や再現とは異なる組みあわせということなのだが、コラージュやブリコラージュにも通じている20世紀が発明した創作方法だとみなされている。山本育夫の編集力によって美術という経糸に美術以外にも広がる問題が緯糸として織られている。文字通りの「つづれ織り」が展開されつつあったのだ。Bゼミや美学校を連想しないわけにはいかない。ある言説や表現の空間を提示することと、それを受けいれる側が「わかる」ことの重要さをあらためて認識させられた。言説や表現のプラットフォームのあり方の問題である。