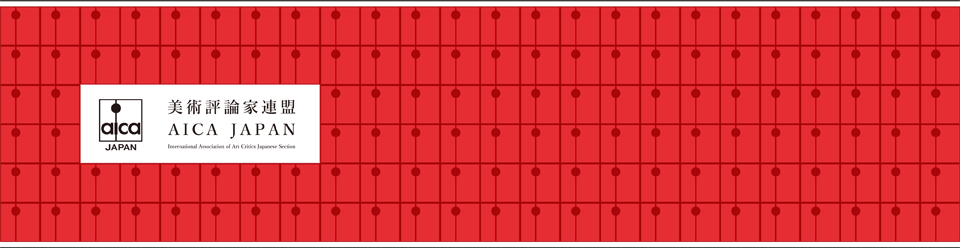美術評論家連盟は1982年4月10日、11日の2日間に亘り、東京・プレスセンターホールにおいて「日英現代美術国際シンポジウム」を開催した。折から東京都美術館で同年2月27日から4月11日まで開催されていた「今日のイギリス美術展」(以下、イギリス展)に連携する形で実現したものであった。当時筆者は会員ではなかったが、イギリス展開催館のひとつ、栃木県立美術館の担当学芸員として同展企画に関わっており、シンポジウムを聴講する機会を得た。直接の当事者ではないが、ごく近い場所にいた者としてこのシンポジウムの意義や問題点を考えてみたい。
イギリス展は1979年度から東京都美術館、栃木県立美術館、国立国際美術館、北海道立近代美術館、北九州市立美術館(調査段階のみ参加、最終的に福岡市美術館で開催)の5館の共同企画として準備作業が進められていた。商業主義に与しない公立館相互の連携と学芸的研究の積み重ねを重視し、ブリティッシュ・カウンシル(以下、B.C.)の全面的な協力のもとに、3年を費やして従来とは全く異なる国際基準の現代美術展が実現した。一人の作家に充分なスペースを与える個展形式の集合という構成や、壁を白く塗り、キャプションはなるべく目立たなくという展示手法など、日本の美術館にとってまさに革命的なものだった。
加えてデイヴィッド・ナッシュとトニー・クラッグの出品作の日本での制作が提案され、筆者はナッシュの雪の奥日光山中での風倒木による制作に3週間立ち会うことになった。クラッグは夢の島で拾得したプラスティック・ゴミから作品を制作、東京都美術館の担当者が対応した。この他にも、マイケル・クレーグ゠マーチン、ナイジェル・ホールらが自作の設置のために来日した。2月末のオープニング直後に、これらの作家たちにテートのキーパーやB.C.の担当官を交えたシンポジウムが開かれ、とりわけナッシュの制作場所の環境を取り込む徹底した自然主義が大きな反響を呼んだ。
連盟サイドから見ると、1977年の段階で「国際的な会議の開催」が、「美術館での展覧会プロジェクト」、「戦後日本美術のドキュメントの編集・出版」と共に事業目標として挙げられていた。とはいえ、具体化への道は遠く、その一方でイギリス展のプロジェクトは着々と進行していた。会員の朝日晃、大島清次、本間正義、村田慶之輔(敬称略)が開催館の要職にあり、岡本謙次郎会長が同展実行委員長の任にあったことで早い段階から情報の共有はなされていた。80年初めには、英米で開催中のイギリス現代展の調査が岡本、村田により行われた。81年夏の段階で出品作家も大筋が決まり、展覧会サイドからの要請もあり、一気に動き出したようだ。同年9月1日付の文書には既にシンポジウムの構成案が明記されている。自己資金を遙かに超える額の資金調達の必要も謳われ、最終的には、会員からの寄付も含め700万円弱の募金を達成している。
シンポジウム第一日はテートのキーパー、ロナルド・アリーの「現代美術の構成的な傾向」についての基調講演、出品作家ジョン・ヒリアードによる講演「現代美術における写真」に次いで、ジョン・ビアズリー(コーコラン美術館)、パターソン・シムス(ホイットニー美術館)、桑原住雄が加わり、岡田隆彦の司会で討議が進められた。第二日は「現代美術と自然」についてのビアズリー、シムスによる基調講演の後、4人の招聘者に大島清次が加わり、三木多聞司会による討議という日程だった。
「現代美術と自然」については、ビアズリーがウォルター・デ・マリア、ロバート・スミッソン、クリストら、アメリカの作家たちの巨大プロジェクトの背後にある文化的背景を切れ味良く論じ、イギリス展出品のナッシュ、リチャード・ロング、ハミッシュ・フルトン、ロジャー・アックリングの密やかなありようとの差異を際立たせた。日本文化における自然との親和性も相俟って、展覧会の内容をより広範な文脈で捉える格好の機会となった。
それに比べ、第一日の「現代美術の構成的な傾向」というテーマ設定は些か説得力を欠いた。アリーの講演は1930年代イギリスにおけるナウム・ガボを介したベン・ニコルソンらによる構成主義の受容を中心に据え、その前史としてのキュビスムと戦後の構成的抽象の多様な展開を辿ったものだったし、ビアズリー、シムスの論議もロシア構成主義の歴史的意味といった問題に終始した。おそらく、日本側の意図は「構成的」という概念を手がかりにアンソニー・カロやフィリップ・キングらを含めたイギリスの絵画・彫刻を通底する幾何学的抽象主義の今日的意義を論ずるということだったのだろうが、完全にすれ違いに終わってしまった。
むしろ、写真のメカニズムを自覚的に捉え、独自の表現に転化するヒリアードの発表もあり、ロング、フルトン、ギルバート&ジョージ、B・ディミトリエーヴィッチといったコンセプチュアリズムとの関連で写真を用いる作家の出品もあっただけに、この枠組みで議論を進めればよりアクチュアルなものになったのではと惜しまれる。
共通のタームによってなんとなく意図は通じたように思っても、その内包するところについての厳密な論議がなかったために生じた誤解であろう。シンポジウム開催から1年半後の1983年10月末に報告書が刊行されている。4人の招聘者の講演原稿もしくは要約が英文のみで掲載され、日本側パネリストと司会の事後の要約ないし感想が和文のみで綴られている。「国際的な会議」と称しつつ、テキストはバイリンガルではないし、シンポジウムの論議の過程も採録されていない。記録としては不十分なものと言わざるを得ない。背景に人的・資金的脆弱さがあることは容易に想像がつく。
評論家連盟として、困難を乗り越えともかくも国際シンポジウム実現に漕ぎ着けたことは評価すべきだろう。とはいえ、今日の美術が直面する諸問題を遠来の気鋭の評論家と共有し、実質的な議論が成立しえたかというと甚だ心許ない。その後、海外への情報発信が加速され、不断に行われるようになったとも聞かない。課題は未解決のまま現在の私たちに遺されている。