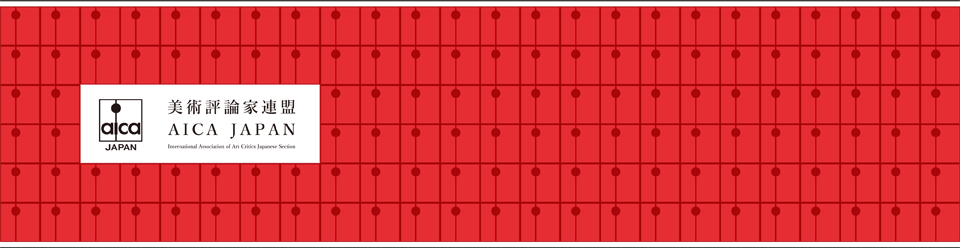平成のいまもなお私たちは黒いミルクをのむ。P.ツェランのこの警句はヒロシマにもうひとつの島を付け加える事態の発生によってなおさら私たち自身の言葉となった。この詩語は、美術館に行けば自由になれる、という幻想を想起させる。だが日常を離れた非日常へと解放する娯楽施設の機能は美術館には基本的にない。日常では覆い隠された現実が作品を通じて開示される場が美術館だからだ。しかしベールで隠された非日常としての美術館は大いに賑わっている。ここでは娯楽の場として定着した美術館と日常を暴く美術館という裂け目が現れる。美術館という概念そのものが分裂している。どちらかが真正の美術館なのではない。両者はコインの裏表の関係にある。
平成における主だった美術館の動きを概観し、美術館と社会の亀裂を確認する。メディアアート系、アウトサイダーアート系、そしてアジア系美術館、さらに日本的に変容した多くの芸術祭が生まれた。これらは既存の近現代美術館が拡張されたものではなく、既存美術館の対案として生まれたものだ。西欧発祥の美術館レジームへのレジスタンスであり、それらへの批評的スタンスを初めから内包している。特に平成に誕生した藁工ミュージアム(高知)や鞆の津ミュージアム(広島)、はじまりの美術館(福島)などに代表されるアウトサイダーアート系美術館は、従来の美術と美術館への反旗の狼煙である。富裕層の誇示手段とその後押しをしてきた美術批評への強烈な批判となっている。これは福祉という社会厚生概念と不可分なことは留意しなければならない。この語の背後に潜む健常者との無差別化というイデオロギーが、狭義の創造性が顕在化した美術と硬冷化したままの創造性との分断の源であったからだ。
折しも東京2020オリンピック・パラリンピックが国家主義的に喧伝されている現在、健常と障害との二分法で美術館を差別の舞台にした昭和の歴史を思い起こさないわけにいかない。大ドイツ美術展と退廃美術展の差別的展示は過去の歴史とみえようとも、国家が美術を何等かの形で後押しする圧力は構造的には何も変わっていない。国内三館は草の根的資金による運営だが、国家が助成金の名目で救いの手を差し出すとき、対立や分断への警戒レベルをあげる必要がある。なぜなら退廃美術展はアウトサイダーアートと現代美術を差別の対象にしていたからだ。
特定の表現を退廃とみなす国家秘密警察はもはや存在しないはずである。それでもなお美術館は監視されている。この監視を表現の昇華によってすり抜けるのが冷戦時代の美術(館)であったのに対して、ベルリンの壁崩壊以降すなわち平成の美術(館)はより直接的になった。冷戦美術のような間接的表現では1%のエリートにしか伝わらない。社会批評性の昇華と洗練の手続き双方の省略が平成の美術の最大の特質である。とすればアーティストと共闘する美術館が社会との軋轢を生むのは当然である。ここでは議論の噴出が展覧会コンセプトとして意図されているからである。
表現の自由を強制的に封じる検閲ではなく、自主規制へと促す手法は、監視と密告の時代の再来を予感させる。検閲は憲法で禁じられているがゆえにない、のではなく巧妙に隠蔽される。監視社会もまた作品の主題となり、展覧会のテーマとなる。それがアーティストと美術館の使命であるからだ。だが、ほどよく昇華された表現・企画は99%に黙殺され、直接的なものは騒動になる。
平成日本に限らず優れた美術作品が騒動になる事例は数多い。そのほとんどは美術の敗北に終わっている。平成末に福島に造立されたヤノベケンジの《サン・チャイルド》しかり。社会的大騒動をまきおこしながら民主的議論の末に作品と美術館が勝利した数少ない例のひとつが、J.ボイスの《汝の傷をみせよ》だ。ほとんどすべての人に縁起でもない心象を与えずにおかない遺体運搬用ベッドのダブルオブジェクトを配したインスタレーションはミュンヘン中心部のクンストフォーラムすなわち公共空間で発表された。この不気味極まりない作品を公立のレーンバッハハウス美術館が購入しようとする。世論は猛反対の嵐であることはいうまでもない。だが一般市民を巻き込んだ激論の末にA.ツヴァイテ館長とボイスは、美術館の収蔵という勝利を勝ち取る。以来、人類史上最も重要な作品のひとつとして同館に常設展示されていることは周知のとおり。
この例が示すのは、美術館とアーティストが確信をもって社会に問う、あるいは挑発するという行為が無理解な社会の前で屈服することなく、根気強く議論の場を開き続けて社会を納得させる強靭な言説を生み出しえるか否かに、美術に携わる者と美術館の存在意義がかかっているということだ。二人のカリスマだけが例外であってはならない。ふるいにかけて残すべきは「美術館に資金が必要なときに、なぜ田舎道を舗装しなければならないのか」という市民の声であり、その逆ではない。マスメディアを歓喜させる巨大な見世物小屋が美術館と思われるようでは、この世に美術館などないも同然であろう。優れた作品とアーティストを萎縮させる美術館それ自体が、退廃美術館と呼ばれる日は遠くない。