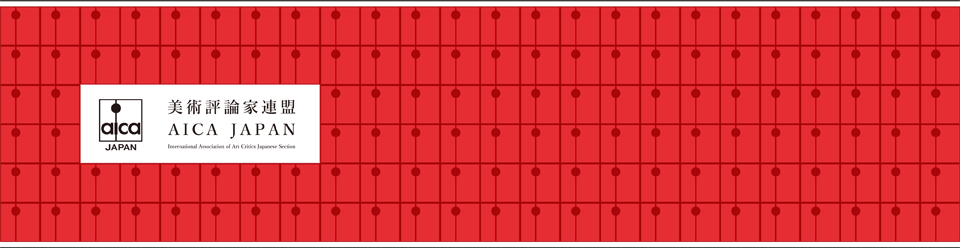「メディア・アート」という言葉が流通し始めて約30年になる。この言葉は、1980年代にコンピュータの高速化によるリアルタイムのグラフィック処理が可能にしたインタラクティヴ・アートの登場を端緒としている。自転車をインターフェイスとしたジェフリー・ショウの《レジブル・シティ》(1989)を皮切りに、インターフェイスが体験者とコンピュータを接続し、その都度異なるプロセスが立ち現れるインタラクティヴ・アートは、観者/作品、人間/環境、実空間/ヴァーチャル空間、生命/非生命などの境界をつなぎ問い直すものであった。
まず1989年という時代を確認する。日本では、年明け直後の天皇崩御とともに「昭和」が終わり「平成」へと移行する。世界的には民主化運動とともに東西冷戦が終結に向かった年であり、6月に中国で天安門事件が起き、11月にベルリンの壁が崩壊、1990年代初頭にかけて中東欧地域で国境が変更され、ソ連も消滅した。
技術・社会的な転換期に生まれたメディア・アートは、90年代に境界横断的な実験場となった。生きた植物や自作のインターフェイス、脳波や脈拍など生体情報の取得、自律的な情報エージェントやヴァーチャルな存在とのインタラクション、描いたドローイングが人工生命体として現れるなど、多くの作品がヴァーチャル・リアリティ(VR)や人工知能(AI)、人工生命(AL)など科学技術に批評的に切り込むことで実現されている。
当時探索されたヴィジョンや問題系は、今も有効である。アートの側面においては、リサーチやプロジェクト・ベース、複数のメンバーによるコラボレーション、プロセスやアーカイヴとしての作品、参加に開かれたプラットフォーム、ヴァージョンアップ、共有文化などが挙げられる。技術的には、様々なデータのセンシング、データの解析や可視化、データベースとしての分類や蓄積、活用などである。
過去30年の技術の進歩は、メディア・アートの領域や展開の場を大きく拡張させた。時代を俯瞰すると、90年代前半、パソコンやインターネットが普及し始めた時代にネット・アートが、当初ブラウザやソースコードへの実験的介入として生み出された。90年代後半にはソフトウェア・アートが出現、インターネットと実空間を結んだサイト・スペシフィックな屋外プロジェクトも開始されている。
21世紀に入ると、公共空間でのインタラクティヴ・プロジェクトやDIYのムーヴメントが活発化する。00年代前半には、合成生物学の進展を背景にバイオ・アートが、後半にはインターネットを日常のリアルとして体現するポスト・インターネット・アートが登場、10年代にはこれらの拡張的展開とともに、最新機材を投入した見世物的(スペクタクル) なプロジェクト(プロジェクション・マッピングなど)が、各地で人を集め、加えて近年のロボット工学やAI、VRの進展を反映した作品が発表されている。
スペクタクルな体験は人々を魅了し易いが、インタラクティヴであるとしても表層的な意味を押し付け、想像の余地を与え難い。バイオ・アートは生命観を問う重要な側面を持つが、遺伝子組換えや人工細胞作成を行う事実も含め、よりオープンな議論が必要である。バイオ・アートやAIを使ったアートは、コードや生命体、知性としての人間自体が対象となるだけでなく、人間と他の生命体(自然であれ人工であれ)や非生命との境界領域という未知の深淵を見せている。それはまた、人間によって生み出された「アート」というものの存在意義を根底から問い直すことを促すはずである。
近年の科学技術の飛躍的な進歩は、メディア・アートにおいても技術優位、エンタテインメント的消費、批評の脆弱化という傾向を強めている。国内では、メディア・アート的な展開も含めたクリエイティヴ企業やエージェンシーへの依存が企業、美術館、地方公共団体ともに高まり、2020年とその後に向けて加速している。最先端の機材や巨額の予算によって可能な実験もあるが、そこで顧みられない多様な実験や営為こそより注視していく必要がある。
メディア・アートは、科学技術の動向に依拠しながらも、直線的に進む科学に常に警告や触発を与えてきた。「アート&サイエンス」は、今も昔もメディア・アートの根幹の一つであるが、近年、科学技術がますます経済論理に取り込まれつつある状況にいかに対応するかが課題となっている。生命科学、AI、VR、宇宙開発など、いずれの分野でも新たな領土化が、疎外される人々や存在を後目に進行しつつある。
さらに世界を覆い尽くしている問題として、GAFA(Google, Apple, Facebook, Amazon)に代表される米国大企業が提供するインフラへの依存とそこでのデータ監視・管理がある。インターネットが普及し始めた90年代に期待された自律的な場から反転した、ディストピア的な無力感が蔓延している。人々が無意識に行動を自粛し、「つながり」や「ケア」の名の下に相互監視を行い、ビッグデータが過去の履歴から次の行動を予測し指し示す社会…。まさにメディア・アートの介入が望まれるが、それが困難なのが今という時代なのである。
メディア・アートの黎明期には、アーティストは技術が未分化であるがゆえに介入が可能であった。技術が高度化し、情報ネットワークが張り巡らされた現在、介入は困難を極める。危機を危機と見なすこと自体が周到に回避され、忘却へと向かう倦怠の中、ぎりぎりの可能性として筆者が思う実践をいくつか以下に挙げておく:既存の機材やシステムに頼らないDIYによる実験、問題を可視化するための絶え間ない批評的介入、アート&サイエンスが人文科学を含め諸領域や人々との対話を開いて行く場の創出。
メディア・アートが、技術のみならず人間、ひいては世界の潜在的可能性を開示するためのまなざしかつ態度であることを、今後に向けてあらためて確認する時期である。
*追記:メディア・アートの修復、再現、アーカイヴの問題については、「メディア・アートのアーカイヴ:課題と展望」(会報、2015)を参照。