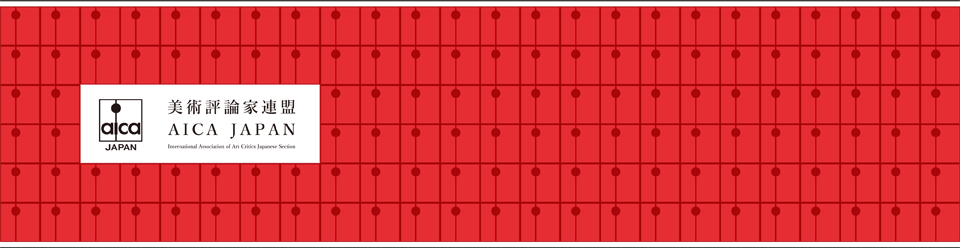私は、大学で建築を学んだ。大学3年のころに出会ったのが、東京都美術館で見た靉嘔(アイオー)の作品《Rainbow Volcano「Rainbow Landscape」1974年》と、月刊『建築文化』(1975年6月号、1977年5月号)に掲載された磯辺行久の「エコロジカル・プランニング特集」だった。
その後、この二人の作家とは、交流することになり、私の人生に大きな影響を与える存在となった。
大学卒業後の私は、山梨清松(東京大学大学院丹下健三研究室出身で丹下健三自邸などの設計に参画した建築家)が主宰する設計事務所に縁があって就職し、退職するまでの35年間、都市計画からランドスケープの設計まで、数多くの仕事に関わることができ、磯崎新アトリエが建築設計を担当したプロジェクトや、都市公園の設計では関根伸夫とも一緒に仕事をすることができた。
私が社会人になりたてのころ、尾崎正教(デモクラート美術家協会の瑛九、靉嘔、磯辺行久らの支援者となり現代美術の啓蒙活動に人生をささげた人物)と綿貫不二夫らが立ち上げた現代版画センターの会員になり、現代美術のコレクションをスタートさせた。そして、私の最初のコレクションは、20代の若者にも手が届く値段で買えた、靉嘔のシルクスクリーン作品《二つのハート 1980年》だった。
当時、北川フラムが、現代版画センターの企画・発行(『’77現代と声(版画の現在)』1978年)で編集し、布野修司(建築系研究者・批評家)との対談で語った言葉「美術とは潜在的に時代を先取りする感覚を形象化したもの」は、『美術とは人類の道しるべ』と解釈し、今では私の座右の銘となっている。
私は、現代美術と出会って40年以上経過したが、その間、多くの作家・作品や美術館学芸員らとの交流をとおして、「美術」の持つ魅力とともに多くのことを学ばせてもらった。そして、私のやるべき役割とは、埋もれている作家や作品を発掘し、その価値を後世に伝えることだと思うようになった。
私は、生業とする仕事とは別に、NPO法人環境芸術ネットワークを47歳で立ち上げ、私財を投じて非営利で運営する現代美術系の「虹の美術館」を静岡(旧清水市)につくり、2000年にオープンさせた。
虹の美術館での最大の成果は、「もの派・石子順造・グループ幻触」の掘り起こし作業だった。
現代美術家の多くが、1968~69年にかけて、一斉に絵画や平面から立体表現に作品を変容させた理由のひとつに、李禹煥や石子順造とともに飯田昭二〈幻触〉の影響が少なからずあったことをつきとめた。
近年までほとんど無名に近かった〈幻触〉の人と作品は、2001年の虹の美術館での展覧会や対談集の発行などが弾みとなり、さらに、峯村敏明、尾野正晴、椹木野衣、建畠晢、中井康之、加治屋健司、川谷承子、成相肇らの研究者、批評家、学芸員によって、『美術手帖』での紹介や、「もの派-再考」(国立国際美術館、2005年)、「TOKYO 1955-1970」(ニューヨーク近代美術館、2012年)、「グルーブ幻触と石子順造1966-1971」(静岡県立美術館、2014年)、「釜山ビエンナーレ2016」(釜山市立美術館、2016年)などの展覧会に採りあげられたことで、〈幻触〉の存在が現代美術の世界でも知られるようになった。
〈幻触〉の主要メンバー5人のうちの3人は、2005年の展覧会「もの派-再考」を見届けたかのように、その後まもなく鬼籍(前田守一2007年、小池一誠2008年、鈴木慶則2010年)に入っていった。
2000年以降にスタートした〈幻触〉の掘り起こし作業が、仮に5年遅れていれば、当事者の声を聞くこともなく作品や資料収集も不可能となり、現代美術史に取りあげられることもなかったかもしれない。
また、晩年の浜口隆一(建築評論家)は、週末になると長時間電話で話をする間柄で、1994年には評論デビューを勧められたが、浜口の急逝によって実現することはなかった。
後に私は、美術出版社(美術手帖)が主催する「芸術評論募集」(1954年創設)の第14回募集(2009年)で入選をはたすことができた。浜口隆一は、「美術評論家連盟」創立メンバーの一人だったので、あの世で私のこれまでの活動を見てくれていると思うと、感慨深いものがある。